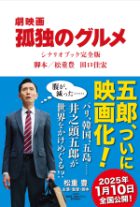「金銭解雇ルール化」で過半数の労働者がトクをする
週刊SPA!連載<第二次正論大戦>
~ 城 繁幸「頭打ち社会への処方箋」 ~
◆一握りの大企業社員&公務員と、圧倒的多数の中小企業社員という身分制度
現在、政府は成長戦略の一環として「金銭解雇のルール化」を検討しているが、企業側と労組が猛反対しているとのこと。金銭解雇とは、例えば年収1年分を支払うことで企業が社員を解雇できるようにするもので、社会全体で労働力を有効に活用できる優れた成長戦略だ。まあクビになりかねない労働組合が反対するのはわかるが、なぜ経営側も反対するのか。そこに、日本の隠れた真実がある。
実は「終身雇用だから会社は従業員をクビにしてはいけない」というルールを守っているのは大手企業や公務員だけであり、中小企業では従業員をクビにするところが割と普通にある。で、政府も事実上、それを黙認している。40年くらい雇い続けろなんてむちゃくちゃなルールは余裕のある大手企業しか守れないのだから、これはしょうがない。
つまり、日本の雇用というのは、ギッチギチに法で保護された大企業・公務員と、ザル状態で放置プレイされている圧倒的多数の中小零細企業という具合に二極化しているわけである。
◆労使対立は虚構。労使がタッグを組む理由
ここで「1年分の賃金を払えばクビにしていいよ」というルールをつくったとする。それで損をするのは誰だろうか。まず、今まではカネなんか払わずクビにできていた中小企業の経営者は(数百万円も払わなきゃならなくなるわけで)大損である。また、65歳まで無条件で雇用が保障されるはずだった大手企業の労組や公務員も、手切れ金でクビになるリスクが発生するわけだから損をする側である。これが、経営者と労組がタッグを組んで反対する理由だ。
一方、トクをする人間は「中小零細企業で働く9割の労働者」であることは明らかだ。彼らは何の保障もなかった代わりに、1年分の給与という強力なセーフティネットを手に入れられるのだから。
重要な成長戦略の柱である労働市場流動化については、よく「解雇規制の緩和」などと呼ばれることもあるが、実際には過半数の労働者の権利を強化する“規制強化”というのが真実なのだ。
面白いのは、共産党や社民党といった、本来は弱者の側に立つべきリベラルな面々が、こうした改革に揃って反対している点だろう。彼らはしょせん大企業労組や公務員といったお金持ちの味方であり、弱者の権利になんかこれっぽっちも興味はないということだ。
今回の労使タッグ結成から見えてくるのは、この国には大企業・公務員とそれ以外という身分制度があり、労使対立なんて貧乏人をガス抜きするためのフィクションだという現実である。
<処方箋>
× 金銭解雇は規制緩和であり、労働者が損をする
↓
○金銭解雇は規制強化であり、過半数の労働者がトクをする
【城 繁幸/じょうしげゆき】
’73年生まれ。人事コンサルティング「Joe’s Labo」代表。『若者はなぜ3年で辞めるのか』(光文社新書)が40万部突破のベストセラーに。『「10年後失業」に備えるためにいま読んでおきたい話』が発売中
※「第二次正論大戦」は週刊SPA!にて好評連載中
この記者は、他にもこんな記事を書いています
ハッシュタグ