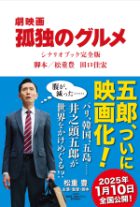世界文化遺産から読み解く世界史【第30回:新しい宗教運動が新しい芸術を生む――アッシジのサン・フランチェスコ聖堂】

アッシジのサン・フランチェスコ聖堂
新しい宗教運動がおこった町アッシジ
フィレンツェの文化が、ヨーロッパの文化の発祥であったということと関連して、フィレンツェに近いトスカーナ州のスパシオ山の斜面につくられたアッシジという都市について触れておきたいと思います。 ここに聖フランチェスコ(1181~1226)という聖人が現れました。もともと彼はこの町の裕福な毛織物商の家に生れた子でした。最初は軍事的な栄光を夢見て、ペルージャとの戦争に加わります。しかし、捕虜となって、熱病にかかり、神の啓示を受けるのです。その後、説教活動を始めると、その考え方がイタリア中に広がって、フランチェスコ派という新しいキリスト教の運動になったのです。これがイタリアにおける新しい信仰運動の基本になったのです。 この信仰運動が文化を創り出す大きな契機となって、アッシジのサン・フランチェスコ聖堂は、ルネサンス絵画の創始者といわれるジョットが新しい絵画を表現し、シモーネ・マルティーニもここで見事な絵画を描き始めました。このように新しい信仰運動が始まると、それを伝える芸術も盛んになるのです。 信仰運動は本来的に文学とは結びつかないものですが、ダンテの「神曲」、ペトラルカの「カンツォニエーレ」のような作品を生み出す背景をつくりました。 一方で、ジョット、シモーネ・マルティーニといった新しい画家たちがここから生み出されて、それがフィレンツェに伝わっていくわけです。アッシジという場所のおもしろさは、そうしたところにあるのです。日本の宗教との相似点
サン・フランチェスコ聖堂は山の中腹にあります。その宗教運動は、同時代の日本の親鸞や法然らの新しい宗教運動と似ているところがあります。 同時に、山岳信仰に近い形をとると、比叡山や高野山で最澄や空海がやった宗教運動と似ているところがあるということもできるのですが、時代的には親鸞や法然の新しい浄土宗の運動と似ているということです。 新しい民衆的な宗教運動が新しい文化をつくり上げること、これがアッシジからフィレンツェへと向かう文化の一つのつながりとなっているのです。 ジョットはパドヴァにおいても創作活動をしますし、ドナテルロもパドヴァで創作活動をしています。イタリア全体にまで及ぶ文化運動というものが、いかに各都市の特徴をさらに伸ばしていくか、この時代の豊かさを感じるのです。 (出典/田中英道著『世界文化遺産から読み解く世界史』育鵬社) 【田中英道(たなか・ひでみち)】 東北大学名誉教授。日本国史学会代表。 著書に『日本の歴史 本当は何がすごいのか』『[増補]日本の文化 本当は何がすごいのか』『[増補]世界史の中の日本 本当は何がすごいのか』『日本史5つの法則』『日本の戦争 何が真実なのか』『聖徳太子 本当は何がすごいのか』『日本文化のすごさがわかる日本の美仏50選』『葛飾北斎 本当は何がすごいのか』ほか多数。
 |
『葛飾北斎 本当は何がすごいのか』 写楽は北斎だった! 世界に最も知られた日本人北斎の知られざる実像に迫る! 
|
ハッシュタグ
ハッシュタグ
おすすめ記事