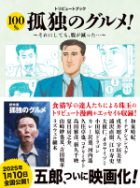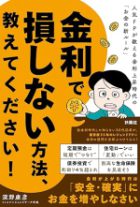憲法を変えなくても法律の改正で対応できる?<憲法改正その前に①>
日本国憲法を「占領憲法」と呼ぶ人もいる。占領憲法などと言われているとさも強引に決められたような印象を抱いてしまうが、手続に関しては民主的なことに驚かれる方もいるのではないだろうか。手続上は、日本国憲法は日本人自身の手によって制定した憲法である。
では、当時の政治情勢はどのようなものだったのか。我が国は戦争に敗れ、昭和20年9月2日に、重光葵が、大日本帝国天皇陛下及び日本国政府の命を受けてサインした文書(いわゆる「降伏文書」)には、天皇及び日本国政府は、連合国最高司令官の制限に置かれると記されている。つまり、ある意味でマッカーサーは「日本国大統領」であったのだ。連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)がNOと言えば、何もできない状況であったともいえる。
この制約の下で日本国憲法は作られた。松本丞治国務大臣が中心となって作成した憲法改正試案(松本試案)は、GHQににべもなく拒絶され、美濃部達吉などの専門家が憲法改正に慎重論を唱えるなか、マッカーサー草案に沿った日本国憲法改正案が策定された。そして先に述べたとおり、ほぼ全会一致で日本国憲法改正案は可決されたのだ。
これが日本国憲法のなりたちである。日本国憲法のなりたちを知ることは大切なことであるが、同じくらい大切なのは、憲法が今の時代に即したものであるか、つまり価値観、技術や周辺環境の変化に適応できているかであろう。
70年前に施行された憲法がそのままでは政策のあり様や現状と矛盾するのであれば、時代に合わせて手入れするのは何ら不自然なことではない。
一方で現状に適応していないとしても、憲法改正を常に必要とするとは限らない。憲法を変えなくても法律や政令の改正で対応できる場合も考えられるし、変えなくてもよいのに変えることは、かえって不合理な事態を招くことすら考えられる。
長く大切に使えば輝くものもあれば、時と共に朽ち果ててしまうものもある。どちらに進むかはその内容次第だ。日本国憲法の内容は、熟年の旨味を出した逸品であるか、それとも単に古びた一品にすぎないのか。私たちは今一度日本国憲法を吟味する必要がある。
【大江弘之】弁護士。1987年生まれ。早稲田大学法学部卒業、東京大学法科大学院修了。第33回土光杯全日本青年弁論大会ニッポン放送杯受賞。一般財団法人ディフェンスリサーチセンター研究委員
1
2
ハッシュタグ