全米で物議を醸している『アメリカン・スナイパー』の謎を解く戦争映画【後編】
⇒【前編】はコチラ
◆路肩爆弾の腹いせにおんな子どもを虐殺
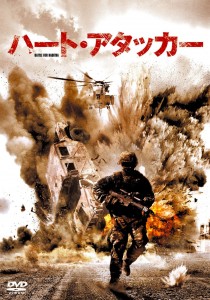 お次は、米海兵隊、過激派、一般市民の3つの視点から実際の虐殺事件を再現した英映画『ハート・アタッカー(原題:ハディサの戦い)』(’07)だ。
同時並行でそれぞれの置かれた立場が見て取れる傑作である。
海兵隊を乗せた軍用車両の一団が路肩爆弾の攻撃を受け、民家の方角からも銃撃されたため、当たりを付けた民家に海兵隊が侵入し、女性や子どもを含む非武装の一般市民24人を殺害した実話に基づいている。
映画は、占領後に失職した中年の元イラク兵ら2人が前金500ドル(成功ならプラス500ドル)欲しさに、IED(即席爆発装置)の設置をアルカイダから請け負うシーンから始まる。アルバイト感覚なのに驚くが、生活レベルが低いので、決して突飛な選択ではないことが描かれる。
一方、一般市民の対応は、我々日本人の庶民感覚とさして違わない。
近所の道路にIEDを埋める先の2人組を目撃するものの、米軍(や警察)に通報すれば過激派からの報復が待っているので関わり合いたくはないのだ。
「米国人に通報すればテロリストに殺される。黙っていたら米国人は反乱者に協力したと言う。どうしたらいいの?」と相談する主婦たちに、地元の年長女性は「分からない」と戸惑う。まさに究極のジレンマだ。
そこまで背景が示された上で路肩爆弾が炸裂する。
米海兵隊員が1人死に、重傷者も出る。民家の一部を不法占拠した2人組から銃撃された海兵隊員はパニックとなり、周囲のイラク人全員が敵に見えてくる。そして、民家に手榴弾を投げ込み、突入するなり女性や子どもに集中砲火を浴びせる凶行に及ぶのだ。もはや悪夢としかいいようがない。
海兵隊員の「仲間をやったな!」という的外れな台詞が印象的だ。
さらに、走っているだけで敵とみなして射殺するシーンがあるが、実際、交戦規定は現場で緩和されるものだったらしく、一般市民でも「携帯電話を持っている」とか「逃げている」だけで蜂の巣になることが珍しくなかった。
お次は、米海兵隊、過激派、一般市民の3つの視点から実際の虐殺事件を再現した英映画『ハート・アタッカー(原題:ハディサの戦い)』(’07)だ。
同時並行でそれぞれの置かれた立場が見て取れる傑作である。
海兵隊を乗せた軍用車両の一団が路肩爆弾の攻撃を受け、民家の方角からも銃撃されたため、当たりを付けた民家に海兵隊が侵入し、女性や子どもを含む非武装の一般市民24人を殺害した実話に基づいている。
映画は、占領後に失職した中年の元イラク兵ら2人が前金500ドル(成功ならプラス500ドル)欲しさに、IED(即席爆発装置)の設置をアルカイダから請け負うシーンから始まる。アルバイト感覚なのに驚くが、生活レベルが低いので、決して突飛な選択ではないことが描かれる。
一方、一般市民の対応は、我々日本人の庶民感覚とさして違わない。
近所の道路にIEDを埋める先の2人組を目撃するものの、米軍(や警察)に通報すれば過激派からの報復が待っているので関わり合いたくはないのだ。
「米国人に通報すればテロリストに殺される。黙っていたら米国人は反乱者に協力したと言う。どうしたらいいの?」と相談する主婦たちに、地元の年長女性は「分からない」と戸惑う。まさに究極のジレンマだ。
そこまで背景が示された上で路肩爆弾が炸裂する。
米海兵隊員が1人死に、重傷者も出る。民家の一部を不法占拠した2人組から銃撃された海兵隊員はパニックとなり、周囲のイラク人全員が敵に見えてくる。そして、民家に手榴弾を投げ込み、突入するなり女性や子どもに集中砲火を浴びせる凶行に及ぶのだ。もはや悪夢としかいいようがない。
海兵隊員の「仲間をやったな!」という的外れな台詞が印象的だ。
さらに、走っているだけで敵とみなして射殺するシーンがあるが、実際、交戦規定は現場で緩和されるものだったらしく、一般市民でも「携帯電話を持っている」とか「逃げている」だけで蜂の巣になることが珍しくなかった。
 当たり前だが、過激派はこういった状況をもプロパガンダとして利用する。
米国への報復感情は高まり、過激派のシンパ・戦闘員は増加する。
米映画『リダクテッド 真実の価値』(’07)では、検問所で射殺された者の大半が一般民だったことに言及したが、これらの不都合な真実が語られないため『アメリカン・スナイパー』では、イラク人は「野蛮人」にしか映らないのである。
◆戦場に行くたびに仲間を失いPTSDに
映画『アメリカン・スナイパー』で描かれるクリスは、原作の「イラク人のために戦ったことなど一度もない。あいつらのことなど、糞喰らえだ」「つくづく思った、私はやはり戦争が大好きなのだと」(クリス・カイル他著『アメリカン・スナイパー』田口俊樹他訳、ハヤカワ文庫)などと異なり、どちらかといえば葛藤するヒーローとして造形されている。
見てくれを意識した原作よりもこちらの方が実像に近いのだろう。
その半面、クリスは何度も何度もイラク行きを希望している。
当たり前だが、過激派はこういった状況をもプロパガンダとして利用する。
米国への報復感情は高まり、過激派のシンパ・戦闘員は増加する。
米映画『リダクテッド 真実の価値』(’07)では、検問所で射殺された者の大半が一般民だったことに言及したが、これらの不都合な真実が語られないため『アメリカン・スナイパー』では、イラク人は「野蛮人」にしか映らないのである。
◆戦場に行くたびに仲間を失いPTSDに
映画『アメリカン・スナイパー』で描かれるクリスは、原作の「イラク人のために戦ったことなど一度もない。あいつらのことなど、糞喰らえだ」「つくづく思った、私はやはり戦争が大好きなのだと」(クリス・カイル他著『アメリカン・スナイパー』田口俊樹他訳、ハヤカワ文庫)などと異なり、どちらかといえば葛藤するヒーローとして造形されている。
見てくれを意識した原作よりもこちらの方が実像に近いのだろう。
その半面、クリスは何度も何度もイラク行きを希望している。
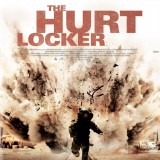 爆弾処理班にスポットを当てた『ハートロッカー』(’07)で、IEDに果敢に立ち向かうウィリアム・ジェームズ一等軍曹(ジェレミー・レナー)が、結局はイラクに舞い戻ったのとまったく同じである。
戦場での高揚感もその理由の一つだが、戦友を守りたい気持ちも強い。だが、戻れば戻った分だけ悲惨な体験が積み重なり、精神がむしばまれることになる。
大義のない戦争では「自分と仲間を守ること」しか動機付けにならない。
クリスの「仲間を守るために殺した」は、逆にいえばそこにしか動機が見出せなかったともいえる。しかし、誰もが無傷でいることなど不可能だ。
その結果が、PTSDであり、現在米国が直面している帰還兵問題なのである。
つまり、『アメリカン・スナイパー』は、イラク戦争という米国(当時のブッシュ政権)が生み出した「負の遺産」を一身に背負った悲劇のスナイパーの伝記映画として理解すべきなのだ。
「米軍では、毎日18人の帰還兵が自殺している。退役軍人省の管轄下で治療を受けている元兵士のうち、毎月1000人が自殺を試みる。自殺する帰還兵のほうが、国外の戦闘で戦死する人よりも多い」(アーロン・グランツ他『冬の兵士―イラク・アフガン帰還米兵が語る戦場の真実』TUP訳、岩波書店)。
こんな無茶苦茶な状況を一体誰がもたらしたのか。
それはあまりにも明白だろう。
文/真鍋 厚
爆弾処理班にスポットを当てた『ハートロッカー』(’07)で、IEDに果敢に立ち向かうウィリアム・ジェームズ一等軍曹(ジェレミー・レナー)が、結局はイラクに舞い戻ったのとまったく同じである。
戦場での高揚感もその理由の一つだが、戦友を守りたい気持ちも強い。だが、戻れば戻った分だけ悲惨な体験が積み重なり、精神がむしばまれることになる。
大義のない戦争では「自分と仲間を守ること」しか動機付けにならない。
クリスの「仲間を守るために殺した」は、逆にいえばそこにしか動機が見出せなかったともいえる。しかし、誰もが無傷でいることなど不可能だ。
その結果が、PTSDであり、現在米国が直面している帰還兵問題なのである。
つまり、『アメリカン・スナイパー』は、イラク戦争という米国(当時のブッシュ政権)が生み出した「負の遺産」を一身に背負った悲劇のスナイパーの伝記映画として理解すべきなのだ。
「米軍では、毎日18人の帰還兵が自殺している。退役軍人省の管轄下で治療を受けている元兵士のうち、毎月1000人が自殺を試みる。自殺する帰還兵のほうが、国外の戦闘で戦死する人よりも多い」(アーロン・グランツ他『冬の兵士―イラク・アフガン帰還米兵が語る戦場の真実』TUP訳、岩波書店)。
こんな無茶苦茶な状況を一体誰がもたらしたのか。
それはあまりにも明白だろう。
文/真鍋 厚
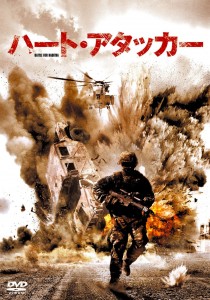 お次は、米海兵隊、過激派、一般市民の3つの視点から実際の虐殺事件を再現した英映画『ハート・アタッカー(原題:ハディサの戦い)』(’07)だ。
同時並行でそれぞれの置かれた立場が見て取れる傑作である。
海兵隊を乗せた軍用車両の一団が路肩爆弾の攻撃を受け、民家の方角からも銃撃されたため、当たりを付けた民家に海兵隊が侵入し、女性や子どもを含む非武装の一般市民24人を殺害した実話に基づいている。
映画は、占領後に失職した中年の元イラク兵ら2人が前金500ドル(成功ならプラス500ドル)欲しさに、IED(即席爆発装置)の設置をアルカイダから請け負うシーンから始まる。アルバイト感覚なのに驚くが、生活レベルが低いので、決して突飛な選択ではないことが描かれる。
一方、一般市民の対応は、我々日本人の庶民感覚とさして違わない。
近所の道路にIEDを埋める先の2人組を目撃するものの、米軍(や警察)に通報すれば過激派からの報復が待っているので関わり合いたくはないのだ。
「米国人に通報すればテロリストに殺される。黙っていたら米国人は反乱者に協力したと言う。どうしたらいいの?」と相談する主婦たちに、地元の年長女性は「分からない」と戸惑う。まさに究極のジレンマだ。
そこまで背景が示された上で路肩爆弾が炸裂する。
米海兵隊員が1人死に、重傷者も出る。民家の一部を不法占拠した2人組から銃撃された海兵隊員はパニックとなり、周囲のイラク人全員が敵に見えてくる。そして、民家に手榴弾を投げ込み、突入するなり女性や子どもに集中砲火を浴びせる凶行に及ぶのだ。もはや悪夢としかいいようがない。
海兵隊員の「仲間をやったな!」という的外れな台詞が印象的だ。
さらに、走っているだけで敵とみなして射殺するシーンがあるが、実際、交戦規定は現場で緩和されるものだったらしく、一般市民でも「携帯電話を持っている」とか「逃げている」だけで蜂の巣になることが珍しくなかった。
お次は、米海兵隊、過激派、一般市民の3つの視点から実際の虐殺事件を再現した英映画『ハート・アタッカー(原題:ハディサの戦い)』(’07)だ。
同時並行でそれぞれの置かれた立場が見て取れる傑作である。
海兵隊を乗せた軍用車両の一団が路肩爆弾の攻撃を受け、民家の方角からも銃撃されたため、当たりを付けた民家に海兵隊が侵入し、女性や子どもを含む非武装の一般市民24人を殺害した実話に基づいている。
映画は、占領後に失職した中年の元イラク兵ら2人が前金500ドル(成功ならプラス500ドル)欲しさに、IED(即席爆発装置)の設置をアルカイダから請け負うシーンから始まる。アルバイト感覚なのに驚くが、生活レベルが低いので、決して突飛な選択ではないことが描かれる。
一方、一般市民の対応は、我々日本人の庶民感覚とさして違わない。
近所の道路にIEDを埋める先の2人組を目撃するものの、米軍(や警察)に通報すれば過激派からの報復が待っているので関わり合いたくはないのだ。
「米国人に通報すればテロリストに殺される。黙っていたら米国人は反乱者に協力したと言う。どうしたらいいの?」と相談する主婦たちに、地元の年長女性は「分からない」と戸惑う。まさに究極のジレンマだ。
そこまで背景が示された上で路肩爆弾が炸裂する。
米海兵隊員が1人死に、重傷者も出る。民家の一部を不法占拠した2人組から銃撃された海兵隊員はパニックとなり、周囲のイラク人全員が敵に見えてくる。そして、民家に手榴弾を投げ込み、突入するなり女性や子どもに集中砲火を浴びせる凶行に及ぶのだ。もはや悪夢としかいいようがない。
海兵隊員の「仲間をやったな!」という的外れな台詞が印象的だ。
さらに、走っているだけで敵とみなして射殺するシーンがあるが、実際、交戦規定は現場で緩和されるものだったらしく、一般市民でも「携帯電話を持っている」とか「逃げている」だけで蜂の巣になることが珍しくなかった。
 当たり前だが、過激派はこういった状況をもプロパガンダとして利用する。
米国への報復感情は高まり、過激派のシンパ・戦闘員は増加する。
米映画『リダクテッド 真実の価値』(’07)では、検問所で射殺された者の大半が一般民だったことに言及したが、これらの不都合な真実が語られないため『アメリカン・スナイパー』では、イラク人は「野蛮人」にしか映らないのである。
◆戦場に行くたびに仲間を失いPTSDに
映画『アメリカン・スナイパー』で描かれるクリスは、原作の「イラク人のために戦ったことなど一度もない。あいつらのことなど、糞喰らえだ」「つくづく思った、私はやはり戦争が大好きなのだと」(クリス・カイル他著『アメリカン・スナイパー』田口俊樹他訳、ハヤカワ文庫)などと異なり、どちらかといえば葛藤するヒーローとして造形されている。
見てくれを意識した原作よりもこちらの方が実像に近いのだろう。
その半面、クリスは何度も何度もイラク行きを希望している。
当たり前だが、過激派はこういった状況をもプロパガンダとして利用する。
米国への報復感情は高まり、過激派のシンパ・戦闘員は増加する。
米映画『リダクテッド 真実の価値』(’07)では、検問所で射殺された者の大半が一般民だったことに言及したが、これらの不都合な真実が語られないため『アメリカン・スナイパー』では、イラク人は「野蛮人」にしか映らないのである。
◆戦場に行くたびに仲間を失いPTSDに
映画『アメリカン・スナイパー』で描かれるクリスは、原作の「イラク人のために戦ったことなど一度もない。あいつらのことなど、糞喰らえだ」「つくづく思った、私はやはり戦争が大好きなのだと」(クリス・カイル他著『アメリカン・スナイパー』田口俊樹他訳、ハヤカワ文庫)などと異なり、どちらかといえば葛藤するヒーローとして造形されている。
見てくれを意識した原作よりもこちらの方が実像に近いのだろう。
その半面、クリスは何度も何度もイラク行きを希望している。
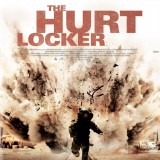 爆弾処理班にスポットを当てた『ハートロッカー』(’07)で、IEDに果敢に立ち向かうウィリアム・ジェームズ一等軍曹(ジェレミー・レナー)が、結局はイラクに舞い戻ったのとまったく同じである。
戦場での高揚感もその理由の一つだが、戦友を守りたい気持ちも強い。だが、戻れば戻った分だけ悲惨な体験が積み重なり、精神がむしばまれることになる。
大義のない戦争では「自分と仲間を守ること」しか動機付けにならない。
クリスの「仲間を守るために殺した」は、逆にいえばそこにしか動機が見出せなかったともいえる。しかし、誰もが無傷でいることなど不可能だ。
その結果が、PTSDであり、現在米国が直面している帰還兵問題なのである。
つまり、『アメリカン・スナイパー』は、イラク戦争という米国(当時のブッシュ政権)が生み出した「負の遺産」を一身に背負った悲劇のスナイパーの伝記映画として理解すべきなのだ。
「米軍では、毎日18人の帰還兵が自殺している。退役軍人省の管轄下で治療を受けている元兵士のうち、毎月1000人が自殺を試みる。自殺する帰還兵のほうが、国外の戦闘で戦死する人よりも多い」(アーロン・グランツ他『冬の兵士―イラク・アフガン帰還米兵が語る戦場の真実』TUP訳、岩波書店)。
こんな無茶苦茶な状況を一体誰がもたらしたのか。
それはあまりにも明白だろう。
文/真鍋 厚
爆弾処理班にスポットを当てた『ハートロッカー』(’07)で、IEDに果敢に立ち向かうウィリアム・ジェームズ一等軍曹(ジェレミー・レナー)が、結局はイラクに舞い戻ったのとまったく同じである。
戦場での高揚感もその理由の一つだが、戦友を守りたい気持ちも強い。だが、戻れば戻った分だけ悲惨な体験が積み重なり、精神がむしばまれることになる。
大義のない戦争では「自分と仲間を守ること」しか動機付けにならない。
クリスの「仲間を守るために殺した」は、逆にいえばそこにしか動機が見出せなかったともいえる。しかし、誰もが無傷でいることなど不可能だ。
その結果が、PTSDであり、現在米国が直面している帰還兵問題なのである。
つまり、『アメリカン・スナイパー』は、イラク戦争という米国(当時のブッシュ政権)が生み出した「負の遺産」を一身に背負った悲劇のスナイパーの伝記映画として理解すべきなのだ。
「米軍では、毎日18人の帰還兵が自殺している。退役軍人省の管轄下で治療を受けている元兵士のうち、毎月1000人が自殺を試みる。自殺する帰還兵のほうが、国外の戦闘で戦死する人よりも多い」(アーロン・グランツ他『冬の兵士―イラク・アフガン帰還米兵が語る戦場の真実』TUP訳、岩波書店)。
こんな無茶苦茶な状況を一体誰がもたらしたのか。
それはあまりにも明白だろう。
文/真鍋 厚
【関連キーワードから記事を探す】
この記者は、他にもこんな記事を書いています






















