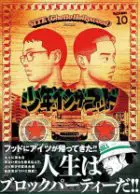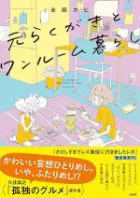『日本という物語』をどう伝えるか【第3回】――豊かな縄文時代像への転換
本書『もう一度学ぶ日本史』は、育鵬社版の中学校歴史教科書を、一般の読者の方に読みやすいよう判型を小ぶりにし、文章をヨコ組みからタテ組みに変え、また図版を精選し再編集したものです。
教科書は文部科学省の検定済(平成27年3月31日付)のため記述の正確性は高く、また、重要なポイントが列記された学習指導要領に即して編集されており、通史として日本史を理解したい人にとっては、格好のテキストとなるのではないかと思います。
さらに、わが国の義務教育のレベルは高く、中学生の教科書といえども侮(あなど)れず、むしろ、読みやすく、分かりやすい本格的な入門書として位置づけられるのではないかと考え刊行しました。
さて、読者の中には、本書に書かれている日本の歴史がかつて学校で習った内容と微妙に違う、と感じられた人も多いのではないかと思います。
縄文時代は貧困だったという思い込みが、教科書に記載されていた
例えば歴史などの授業では、原始・古代の縄文時代は食生活も不安定な、世界の同時代の文明と比べて劣った社会だったという「縄文貧困説」で教えられたのではないでしょうか。あるいは、近世については、ムシロ旗を立てて一揆を繰り返す江戸時代の貧しき農民という「江戸貧農史観」で学習したのではないかと思います。 しかし、近年の実証的な研究はこれらのイメージが正しくないことを指摘しています。にもかかわらず教育現場では従来の説の影響が根強く残っており、それに対して本書(育鵬社の歴史教科書)は、実証的な研究に基づき記述を行っていることが大きな特色となっています。 では最初に、縄文時代から見ていきましょう。例えば、定評のある高校の日本史教科書でも、昭和59年版では「縄文時代は、狩猟・漁撈・採集の段階にとどまり、生産力は低かった。動物や食物資源の獲得は、自然条件に左右されることが多く、人々は不安定できびしい生活をおくっていた……」と記述されていました。 しかし、こうした縄文貧困説は、平成4年から始まった青森県の三内丸山遺跡の本格的な発掘を契機に、明確に覆されていきます。むしろ逆に、発掘調査により、「豊かな縄文文化」の実像が明らかになりました。 民族学者として高名であった佐々木高明氏(元国立民族学博物館館長)は、三内丸山遺跡における数々の発見により、縄文文化は「世界でも第一級の『豊かな狩猟採集民』の文化であることを改めて確認した」(『縄文文化と日本人』講談社学術文庫、317頁、平成13年刊)と記し高く評価しています。栽培、定住による豊かなライフスタイル
育鵬社の歴史教科書では、縄文時代研究の大家である小林達雄氏(国学院大学名誉教授)の監修のもと、縄文時代の実証的な研究成果をふんだんに取り入れました。 まず、原始・古代の章扉には、遺跡から出土した縄文時代の丸木舟の写真を掲載し、当時の漁業や内外の交易に丸木舟が用いられたことを生徒に気付かせるようにしています。 次に、縄文時代の本文記述は以下の通りです。 「縄文時代の人々の生活は、魚介類をとったり、狩猟や採集を中心とするものでしたが、クリの木などを管理し、アサやヒエなども栽培していました。また、干物や塩漬けなどの保存食……をつくる技術ももっていました。こうした食料をたくわえる技術の向上は、人々の定住とムラの発達をうながしました」(太字は引用者、以下同じ) 最初の太字のクリの木などを管理しというのは重要な記述です。縄文人は、元々日本列島に自生していたクリの木を管理しながら、栄養価の高い実は食料に、乾燥させると堅くなって水に強い樹木は建材に用いていました。 こうした事例と共に、2番目の太字の食物の栽培、3番目の太字の定住も縄文時代についての重要な点です。(4に続く) (文責・育鵬社編集部M)
 |
『もう一度学ぶ日本史』 [決定版]大人のための歴史教科書 
|
ハッシュタグ
おすすめ記事