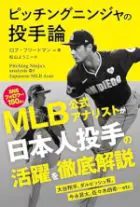日本と海外でこんなに違う「出前一丁」。香港では40種類以上も
コンビニやスーパーには、さまざまな種類の即席麺が並ぶ。麺の量、味付け、パッケージなど、各メーカーが趣向を凝らした商品が並び、激しい競争が繰り広げられている。
そうしたなか、1968年の発売以来、ロングセラーを続けているのが日清食品の「出前一丁」だ。しょうゆベースのコクのあるスープと、食欲をそそる「ごまラー油」が特長の本商品は、日本はもちろん、海外でも人気を博している。じつは、香港においては“ソウルフード”と呼ばれているほどで、即席麺の売上No.1ブランドとして香港の人々の生活に深く浸透しているという。
出前一丁のブランド責任者である、日清食品株式会社 マーケティング部 ブランドマネージャー 土岡洋平さんに、出前一丁がロングセラーを続けるワケや、日本と海外での商品の違いについて話を聞いた。
 出前一丁が誕生したのは、明星食品「明星チャルメラ」やサンヨー食品「サッポロ一番」などが発売され、即席麺メーカー各社が激しい競争を繰り広げていた1960年代後半。数ある商品の中で出前一丁が支持された理由は、「商品としての完成度の高さとごまラー油という付加価値によって、他の商品と差別化を図ることができた」ことにあると土岡さんは話す。
「出前一丁の麺の開発にあたっては、国産の小麦粉はもちろん、外国産の小麦粉も入手可能なものすべてを吟味し、これは!と思うものがあると生産ラインにのせて何度も試作を繰り返したそうです。その結果、その後の日清食品の商品の原型となるような品質の高い麺が完成しました。
また、既存商品と差別化を図るために生まれたアイデアがごまラー油です。ゴマ油をベースに13種類の味をプラスした特製のごまラー油を仕上げに加えることで生まれる“やみつき”な味わいがお客様からご好評をいただき、数多くの即席麺が発売されるなかでしっかりとブランドの認知を獲得し、大人気商品になっていきました」
日清食品の創業者・安藤百福が1958年に発明した世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」は、麺にスープを染み込ませた着味麺だ。
調味料などを加える必要がなく、お湯をかけるだけで、いつでも簡単に美味しいラーメンが食べられる。これこそが、チキンラーメンの醍醐味である。
それに対し、出前一丁は“お湯をかける”のではなく“鍋で調理する”タイプの商品だ。
麺を鍋で茹でた後に粉末スープをいれ、ごまラー油をかけたあと、好みに応じてねぎやのりなどの具材をトッピングし、自分好みのラーメンに仕立てて食べることができる。このように、カスタマイズ性に優れていることが出前一丁の大きな特徴だ。
さらに、パッケージに描かれているキャラクター「出前坊や」も、出前一丁が発売された当初から、ブランドのアイコンとして親しまれている。
「『出前坊や』をデザインしたのは、創業者・安藤百福の息子である安藤宏基(現 日清食品ホールディングス 社長・CEO)です。商品のネーミングについても、安藤百福創業者は“出前ラーメン”や“ラーメン天国”などの案を検討していたそうですが、『どうもしっくりこない』ということで、“出前”の下に威勢の良さを感じさせる“一丁”を付けた出前一丁というネーミングを安藤宏基CEOが提案したんだそうです」
1969年、香港で出前一丁が販売されると瞬く間に人気を集めた。1984年には現地法人を設立し、翌年から香港で生産するほどの成長を遂げていく。
なぜ、特に香港で出前一丁が受け入れられたのか。
土岡さんは「香港では麺類を日常的に食べる習慣があったことや、ごまラー油が一般家庭で調味料としてよく使われていたことが大きい」と説明する。
「アジア圏ではもともと麺文化が根付いていたので、海外展開を考えるにあたって、アジア諸国のマーケットは非常に重要性が高かったんだと思います。
香港市場に進出した際、即席麺市場をリードしていたのは永南食品(現在は日清食品グループの一員)が製造・販売する湯かけタイプの商品でした。後発となる出前一丁は、鍋で煮て調理することで生まれる『麺のもちもちとした食感』や『歯ごたえ』などを訴求したところ高い評価を得ることができたんです。一般家庭で大人気になった出前一丁は、料理人にも好まれ、飲食店でも『食材』のひとつとして使われるようになりました。現在、香港の屋台や飲食店には出前一丁とさまざまな食材を組み合わせたメニューがあるほど浸透しています」
出前一丁が誕生したのは、明星食品「明星チャルメラ」やサンヨー食品「サッポロ一番」などが発売され、即席麺メーカー各社が激しい競争を繰り広げていた1960年代後半。数ある商品の中で出前一丁が支持された理由は、「商品としての完成度の高さとごまラー油という付加価値によって、他の商品と差別化を図ることができた」ことにあると土岡さんは話す。
「出前一丁の麺の開発にあたっては、国産の小麦粉はもちろん、外国産の小麦粉も入手可能なものすべてを吟味し、これは!と思うものがあると生産ラインにのせて何度も試作を繰り返したそうです。その結果、その後の日清食品の商品の原型となるような品質の高い麺が完成しました。
また、既存商品と差別化を図るために生まれたアイデアがごまラー油です。ゴマ油をベースに13種類の味をプラスした特製のごまラー油を仕上げに加えることで生まれる“やみつき”な味わいがお客様からご好評をいただき、数多くの即席麺が発売されるなかでしっかりとブランドの認知を獲得し、大人気商品になっていきました」
日清食品の創業者・安藤百福が1958年に発明した世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」は、麺にスープを染み込ませた着味麺だ。
調味料などを加える必要がなく、お湯をかけるだけで、いつでも簡単に美味しいラーメンが食べられる。これこそが、チキンラーメンの醍醐味である。
それに対し、出前一丁は“お湯をかける”のではなく“鍋で調理する”タイプの商品だ。
麺を鍋で茹でた後に粉末スープをいれ、ごまラー油をかけたあと、好みに応じてねぎやのりなどの具材をトッピングし、自分好みのラーメンに仕立てて食べることができる。このように、カスタマイズ性に優れていることが出前一丁の大きな特徴だ。
さらに、パッケージに描かれているキャラクター「出前坊や」も、出前一丁が発売された当初から、ブランドのアイコンとして親しまれている。
「『出前坊や』をデザインしたのは、創業者・安藤百福の息子である安藤宏基(現 日清食品ホールディングス 社長・CEO)です。商品のネーミングについても、安藤百福創業者は“出前ラーメン”や“ラーメン天国”などの案を検討していたそうですが、『どうもしっくりこない』ということで、“出前”の下に威勢の良さを感じさせる“一丁”を付けた出前一丁というネーミングを安藤宏基CEOが提案したんだそうです」
1969年、香港で出前一丁が販売されると瞬く間に人気を集めた。1984年には現地法人を設立し、翌年から香港で生産するほどの成長を遂げていく。
なぜ、特に香港で出前一丁が受け入れられたのか。
土岡さんは「香港では麺類を日常的に食べる習慣があったことや、ごまラー油が一般家庭で調味料としてよく使われていたことが大きい」と説明する。
「アジア圏ではもともと麺文化が根付いていたので、海外展開を考えるにあたって、アジア諸国のマーケットは非常に重要性が高かったんだと思います。
香港市場に進出した際、即席麺市場をリードしていたのは永南食品(現在は日清食品グループの一員)が製造・販売する湯かけタイプの商品でした。後発となる出前一丁は、鍋で煮て調理することで生まれる『麺のもちもちとした食感』や『歯ごたえ』などを訴求したところ高い評価を得ることができたんです。一般家庭で大人気になった出前一丁は、料理人にも好まれ、飲食店でも『食材』のひとつとして使われるようになりました。現在、香港の屋台や飲食店には出前一丁とさまざまな食材を組み合わせたメニューがあるほど浸透しています」
ごまラー油の味と香りが“やみつき”に
 出前一丁が誕生したのは、明星食品「明星チャルメラ」やサンヨー食品「サッポロ一番」などが発売され、即席麺メーカー各社が激しい競争を繰り広げていた1960年代後半。数ある商品の中で出前一丁が支持された理由は、「商品としての完成度の高さとごまラー油という付加価値によって、他の商品と差別化を図ることができた」ことにあると土岡さんは話す。
「出前一丁の麺の開発にあたっては、国産の小麦粉はもちろん、外国産の小麦粉も入手可能なものすべてを吟味し、これは!と思うものがあると生産ラインにのせて何度も試作を繰り返したそうです。その結果、その後の日清食品の商品の原型となるような品質の高い麺が完成しました。
また、既存商品と差別化を図るために生まれたアイデアがごまラー油です。ゴマ油をベースに13種類の味をプラスした特製のごまラー油を仕上げに加えることで生まれる“やみつき”な味わいがお客様からご好評をいただき、数多くの即席麺が発売されるなかでしっかりとブランドの認知を獲得し、大人気商品になっていきました」
日清食品の創業者・安藤百福が1958年に発明した世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」は、麺にスープを染み込ませた着味麺だ。
調味料などを加える必要がなく、お湯をかけるだけで、いつでも簡単に美味しいラーメンが食べられる。これこそが、チキンラーメンの醍醐味である。
それに対し、出前一丁は“お湯をかける”のではなく“鍋で調理する”タイプの商品だ。
麺を鍋で茹でた後に粉末スープをいれ、ごまラー油をかけたあと、好みに応じてねぎやのりなどの具材をトッピングし、自分好みのラーメンに仕立てて食べることができる。このように、カスタマイズ性に優れていることが出前一丁の大きな特徴だ。
出前一丁が誕生したのは、明星食品「明星チャルメラ」やサンヨー食品「サッポロ一番」などが発売され、即席麺メーカー各社が激しい競争を繰り広げていた1960年代後半。数ある商品の中で出前一丁が支持された理由は、「商品としての完成度の高さとごまラー油という付加価値によって、他の商品と差別化を図ることができた」ことにあると土岡さんは話す。
「出前一丁の麺の開発にあたっては、国産の小麦粉はもちろん、外国産の小麦粉も入手可能なものすべてを吟味し、これは!と思うものがあると生産ラインにのせて何度も試作を繰り返したそうです。その結果、その後の日清食品の商品の原型となるような品質の高い麺が完成しました。
また、既存商品と差別化を図るために生まれたアイデアがごまラー油です。ゴマ油をベースに13種類の味をプラスした特製のごまラー油を仕上げに加えることで生まれる“やみつき”な味わいがお客様からご好評をいただき、数多くの即席麺が発売されるなかでしっかりとブランドの認知を獲得し、大人気商品になっていきました」
日清食品の創業者・安藤百福が1958年に発明した世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」は、麺にスープを染み込ませた着味麺だ。
調味料などを加える必要がなく、お湯をかけるだけで、いつでも簡単に美味しいラーメンが食べられる。これこそが、チキンラーメンの醍醐味である。
それに対し、出前一丁は“お湯をかける”のではなく“鍋で調理する”タイプの商品だ。
麺を鍋で茹でた後に粉末スープをいれ、ごまラー油をかけたあと、好みに応じてねぎやのりなどの具材をトッピングし、自分好みのラーメンに仕立てて食べることができる。このように、カスタマイズ性に優れていることが出前一丁の大きな特徴だ。
香港の飲食店では出前一丁が「食材」のひとつになっている
1986年生まれ。立教大卒。ビジネス、旅行、イベント、カルチャーなど興味関心の湧く分野を中心に執筆活動を行う。社会のA面B面、メジャーからアンダーまで足を運び、現場で知ることを大切にしている
記事一覧へ
記事一覧へ
【関連キーワードから記事を探す】
この記者は、他にもこんな記事を書いています