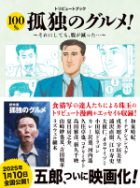高校野球監督をヘッドコーチに招へいした日ハムの勝算
―[山田ゴメス]―
これは去年のソフトボール出身選手の獲得に続いてのサプライズだ!
北海道日本ハムファイターズが仰天人事。なんと! 来季からのヘッドコーチに、プロのコーチ経験がまったくない、現役高校野球監督(48)を招へいしたのだ。氏は、東農大二高から83年、ドラフト3位で投手としてヤクルトに入団。10年間で17勝を挙げ、引退。その後、通信教育で教員資格を取り、つくば秀英高、川越東高で野球部監督を務めているという経歴の持ち主だ。
まるで漫画である。昔、水島新司先生作の『光の小次郎』という漫画で、草野球の監督がプロ監督になるという設定があったけど、まさにそれを地でいくような“事件”が現実に起きてしまった。野球漫画オタクのゴメス記者としては、ワクワク感満点の破天荒な展開。昨今の閉塞したプロ野球界の壁をぶち破る“勇気ある挑戦”だと考える。いろんな賛否両論も飛び交っているようだが、エールの意味も込めて、高校野球監督起用の“勝算”を、ここでは希望的観測も含め、考察してみたい。
(1)“若手の才能を見抜き、育てる”能力はプロ野球よりむしろ高校野球指導者のほうが優れている
そう。高校生は全員が若手なのだ。そして、そんな若手が毎年何十人も部員として入部してくるのだ。そのなかから、レギュラークラスの潜在能力を秘める者を見抜き、育てるノウハウは、きっとプロでも役立つに違いない。
(2)ヘタなプロコーチ経験がないので、新鮮な目で采配を振れる
プロ指導者たちのあいだで長年培われてきた“常識”に縛られなくて済む。現に、『ラストイニング』という高校野球漫画に登場する、理路整然とした戦略の数々は、プロ選手や指導者の目にも、たいそう目新しく映るらしい。
(3)高校野球指導者は、誰もが野球エリートではなく“雑草”である
プロ野球選手としてそれなりの実績を残し、引退後に指導者としてプロ球界に残れた人たちは、結局のところ“野球エリート”なのである。逆に言えば、そういう指導者は現役時代の成功体験とプライドにどうしても縛られがち。“プロになれなかった、生き残れなかった”という挫折を一度味わっている高校野球指導者なら、エリート集団からあぶれてしまった“エリート内雑草”を適確に査定し、再生してくれる、かもしれない。
(4)“一試合負けたらおしまい”というシビアさをプロ球界にも注入!
一年に144試合を行うプロ野球にとって、ときには上手い負け方があるのはわかる。でも、目の前の一試合一試合を全力で戦うトーナメント野球のハングリーさも必要なのではないか? 僕が大好きな言葉「一試合完全燃焼」(byアストロ球団)の根性を、ぜひプロでも育んでもらいたい。
(5)声だしとかチームワークとか、基本の「基」をあらためてたたき込んでくれそう
プロ入りすると、もはや忘れてしまいがちな“高校球児の精神”を今一度思いだしてもらいたい。それだけでもチームのムードはガラッと変わるはずだ。
単なる話題づくりで終わってしまう可能性だってなくはない。だが、来季の日ハムが、高校野球監督出身コーチの影響で、どう変わっていくのか、ゴメス記者としてはじっくりと見定めていきたいところだ。願わくば、この手のサプライズは、FA宣言選手ばっか買い漁っている我が阪神タイガースにこそ、して欲しかったのだが……。<取材・文/山田ゴメス>
 【山田ゴメス】
1962年大阪府生まれ。マルチライター。エロからファッション、音楽&美術評論まで幅広く精通。西紋啓詞名義でイラストレーターとしても活躍。日刊SPA!ではブログ「50にして未だ不惑に到らず!」(https://nikkan-spa.jp/gomesu)も配信中。現在「解決!ナイナイアンサー」(日本テレビ系列)(http://www.ntv.co.jp/99answer/)に“クセ者相談員”として出演。『クレヨンしんちゃん たのしいお仕事図鑑』(双葉社)も好評発売中!大阪府生まれ。年齢非公開。関西大学経済学部卒業後、大手画材屋勤務を経てフリーランスに。エロからファッション・学年誌・音楽&美術評論・人工衛星・AI、さらには漫画原作…まで、記名・無記名、紙・ネットを問わず、偏った幅広さを持ち味としながら、草野球をこよなく愛し、年間80試合以上に出場するライター兼コラムニスト&イラストレーターであり、「ネットニュースパトローラー(NNP)」の肩書きも併せ持つ。『「モテ」と「非モテ」の脳科学~おじさんの恋はなぜ報われないのか~』(ワニブックスPLUS新書)ほか、著書は覆面のものを含めると50冊を超える。保有資格は「HSP(ハイリー・センシテブ・パーソンズ)カウンセラー」「温泉マイスター」「合コンマスター」など
【山田ゴメス】
1962年大阪府生まれ。マルチライター。エロからファッション、音楽&美術評論まで幅広く精通。西紋啓詞名義でイラストレーターとしても活躍。日刊SPA!ではブログ「50にして未だ不惑に到らず!」(https://nikkan-spa.jp/gomesu)も配信中。現在「解決!ナイナイアンサー」(日本テレビ系列)(http://www.ntv.co.jp/99answer/)に“クセ者相談員”として出演。『クレヨンしんちゃん たのしいお仕事図鑑』(双葉社)も好評発売中!大阪府生まれ。年齢非公開。関西大学経済学部卒業後、大手画材屋勤務を経てフリーランスに。エロからファッション・学年誌・音楽&美術評論・人工衛星・AI、さらには漫画原作…まで、記名・無記名、紙・ネットを問わず、偏った幅広さを持ち味としながら、草野球をこよなく愛し、年間80試合以上に出場するライター兼コラムニスト&イラストレーターであり、「ネットニュースパトローラー(NNP)」の肩書きも併せ持つ。『「モテ」と「非モテ」の脳科学~おじさんの恋はなぜ報われないのか~』(ワニブックスPLUS新書)ほか、著書は覆面のものを含めると50冊を超える。保有資格は「HSP(ハイリー・センシテブ・パーソンズ)カウンセラー」「温泉マイスター」「合コンマスター」など
この連載の前回記事
この記者は、他にもこんな記事を書いています
ハッシュタグ