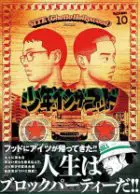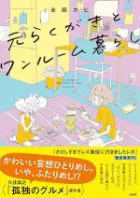港の整備が「まち」を作る: 小名浜の港湾イノベーション5

小名浜港の変遷─ ( 4 ) 日本発の石炭火力イノベーションIGCC
こうして「国家プロジェクト」として「最大の石炭輸入港」となった小名浜港は今、東日本を中心とした日本各地の港に石炭を転送する重要基地となった。 だが、小名浜における火力発電能力をさらに高めていくことで、効果的に日本の火力発電能力それ自体を高めていくことが、もちろん可能となる。 そうした趣旨から、小名浜周辺では今、多くの火力発電所が増強されているところなのだが、石炭火力発電それ自体には、まだまだ技術革新が求められているのが実状だ。 そもそも国内の発電の主力は、CO2排出量が比較的少ないLNG(シェアは5割弱)なのだが、輸送や採掘地開発に関するコストが高く、安定的に十分な量を輸入し続けることが必ずしも容易ではない。 その点、石炭は世界中の埋蔵量が多く、輸送等のコストはLNGよりも低廉であるため、一定程度、石炭火力を増やしていくことには合理性がある。 しかし、石炭火力はCO2を多く排出してしまうことから、政府が地球温暖化対策に取り組んでいる日本では、「現状の石炭火力発電の能力」では、現状3割程度の石炭火力のシェアをこれ以上拡大できない、という状況にある。 ここで、もしも石炭火力発電の「発電効率」を高めることができるなら、つまり、一定量の石炭からより多くの電気が発電できるような技術開発=イノベーションがあれば、単位発電量当たりのCO2排出量を減らすことができる。 その結果、わが国は資源調達の安定性を向上させることが可能となる。小名浜の勿来石炭火力発電所の「IGCC」(石炭ガス化複合発電)
こうした背景の下で今、日本を代表する石炭基地・小名浜の勿来石炭火力発電所(常磐共同火力㈱)に10番目の発電機として設置されたのが「IGCC」(石炭ガス化複合発電)であった。 IGCCは、現状42%といわれる石炭火力の発電効率を48~50%程度にまで上昇させる新技術。これは通常石油発電とほぼ同様のCO2排出量となり、結果、石炭火力の最大のデメリットであった環境負荷を大きく軽減できることになる。 IGCCは、石炭を燃やして水蒸気を作り、その力でタービンを回して発電する、という従来の方式とは異なり、石炭をガス化し、そのガスを利用して「ガスタービン」を回すと同時に、ガスタービンの排熱を利用して蒸気を作って「蒸気タービン」を回し、両者の力を合わせて利用して、より効率的に発電するものである。 小名浜の勿来発電所のIGCCは、実験段階で「世界ではじめて」成功した発電所であると共に、実際の発電に活用されている日本初かつ唯一の商用炉である。 今、日本ではこの小名浜の勿来発電所の経験を踏まえ、さらなるIGCC発電所の建設が進められている。つまり、小名浜港は今、日本のエネルギー業界の構造を改変するイノベーションをもたらす、重要なエネルギー基地にもなっているのである。 藤井聡著『インフラ・イノベーション』(育鵬社刊より) 著者紹介。1968 年奈良県生まれ。京都大学大学院教授(都市社会工学専攻)。第2次安倍内閣で内閣官房参与(防災・減災ニューディール担当)を務めた。専門は公共政策に関わる実践的人文社会科学。著書には『コンプライアンスが日本を潰す』(扶桑社新書)、『強靭化の思想』、『プライマリー・バランス亡国論』(共に育鵬社)、『令和日本・再生計画 前内閣官房参与の救国の提言』(小学館新書)など多数。ハッシュタグ
おすすめ記事