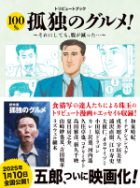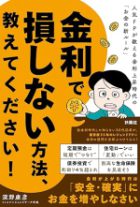介護保険制度が始まるまで、ヘルパーは公務員だった「利用者の入浴介助さえできず」
新人ヘルパーとして先輩から受けた洗礼
 「採用された頃は、ホームヘルパーは、生活保護世帯にしか行けませんでした。利用料はタダです。その後、制度が変わり、生活保護世帯以外にも訪問できるようになりました。当時のホームヘルパーは、1人親家庭・障害者家庭・高齢者家庭のどの家庭にも入っていました」
そのため、サービスの対象は0歳~80歳位までと幅広かったという。トータルで8年間勤務するが、その間で孤独死された5人を発見することになる。
「そういった孤独死に遭遇したのは、全員、公務員時代のことです」
褥瘡(床ずれ)は骨まで見えるほどひどい人が多く、新人教育では、先輩たちから度胸試しをされた。
「外した入れ歯を素手で受け取ったり、普段は自転車移動するところをを徒歩で歩かされたりと、度胸や体力がなければできないので、適性検査のようなものだったんでしょうね」
「採用された頃は、ホームヘルパーは、生活保護世帯にしか行けませんでした。利用料はタダです。その後、制度が変わり、生活保護世帯以外にも訪問できるようになりました。当時のホームヘルパーは、1人親家庭・障害者家庭・高齢者家庭のどの家庭にも入っていました」
そのため、サービスの対象は0歳~80歳位までと幅広かったという。トータルで8年間勤務するが、その間で孤独死された5人を発見することになる。
「そういった孤独死に遭遇したのは、全員、公務員時代のことです」
褥瘡(床ずれ)は骨まで見えるほどひどい人が多く、新人教育では、先輩たちから度胸試しをされた。
「外した入れ歯を素手で受け取ったり、普段は自転車移動するところをを徒歩で歩かされたりと、度胸や体力がなければできないので、適性検査のようなものだったんでしょうね」
お風呂に入れることすらできなかった当時の介護サービス
立教大学卒経済学部経営学科卒。「あいである広場」の編集長兼ライターとして、主に介護・障害福祉・医療・少数民族など、社会的マイノリティの当事者・支援者の取材記事を執筆。現在、介護・福祉メディアで連載や集英社オンラインに寄稿している。X(旧ツイッター):@Thepowerofdive1
記事一覧へ
記事一覧へ
この記者は、他にもこんな記事を書いています
ハッシュタグ