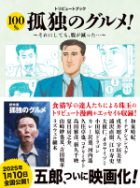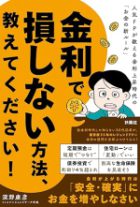人はなぜ「座右の銘」を求めるのか?
―[オレだけの[座右の銘]大事典]―
近頃やたら目につく名言本。この混迷の時代、やはり指針となる言葉が必要とされているのか。ベテラン編集者であり著述家でもある石黒謙吾氏に「自分だけの座右の銘」を伺った
◆名言を知り抜いた著述家&編集者が語る“座右の銘の極意”とは?
人はなぜ座右の銘を求めるのか? それは、言葉という「記号」で自分を鼓舞したり、安心させることができるからだと思います。
多くの人が、いい意味で何かに依存して生きていて、それはお酒でも音楽でも何でもいいんですが、その依存の対象のひとつとして座右の銘があるのでしょう。
座右の銘に選ばれやすい傾向があるのは、やはり短いフレーズでパッと頭に入ってくる言葉ですが、個人的には、たとえばジョン・オズボーンの「人の心はパラシュートのようなものだ。開かなければ使えない」のように、何かに見立てた表現は知的で好きですね。
僕自身の座右の銘は、最初に誰が言ったか、はっきりしないのですが、「カネを残すは銅、仕事を残すは銀、人を残すは金」という言葉。僕がプロデュース&編集を手がける本は著者にとって処女作である場合も多く、その方の人生のターニングポイントとなることもあり、著者にとっても僕にとっても強く記憶に刻まれます。「人を残す」と言うと偉そうですが、人の思い出に残れる生き様には価値があるなと実感し、座右の銘にしています。この言葉が生き方の指標になっているので、極端な話、お金への執着がなくなりましたし、考え方がブレなくなりましたね。
でも座右の銘を、名刺を配るようにいろいろな場で口に出すのは少々ダサいと感じます。その言葉が安っぽくなってしまうので、聞かれたら答えるぐらいがちょうどいいんじゃないでしょうか。
<座右の銘>
カネを残すは銅、仕事を残すは銀、人を残すは金
【石黒謙吾氏】
著述家、編集者。著書と、プロデュースした本は約200冊。近著は名言と写真を絡めた『あいつの気持ちがわかるまで』(宝島社)
取材・文/石島律子 漆原直行 昌谷大介 イラスト/坂本千明
― オレだけの[座右の銘]大事典【7】 ―
 |
『あいつの気持ちがわかるまで』 対人関係のキモが見えてくる 
|
この特集の前回記事
ハッシュタグ