ひろゆきが語る「金子勇とWinny事件」日本にとって”大きすぎる損失”とは?
映画「Winny」が公開されるなど、”不世出の天才プログラマー”として知られる金子勇氏を再評価する動きが広がっている。金子氏は凄腕のプログラマーとしてソフトウェアの研究開発で活躍していたが、2002年に自ら開発したファイル交換ソフト「Winny」が社会問題化し、2004年に京都府警に逮捕・起訴。その後、長年の裁判を戦い抜き無罪を勝ち取るも、2013年に急性心筋梗塞で死去した。
42歳の若さでこの世を去った金子氏に対しては、今でも「もし彼が生きていたら…」という声が多い。ひろゆき氏もその一人であり、「Winny事件と金子さんの喪失は、日本のITの行方を決定づける出来事になりました」と話す。
ここではひろゆき氏の新刊「ざんねんなインターネット 日本をダメにした『ネット炎上』10年史」のなかから、金子勇氏について語るパートを抜粋・掲載する。
社会問題にもなったファイル交換ソフト「Winny」。その開発により著作権法違反ほう助罪に問われていた金子勇さんの無罪が確定したのが、2011年末のことでした。
僕は昔、金子さんに一回だけ会ったことがあります。たしか、金子さんが逮捕されて裁判中で、弁護士の壇俊光先生も同席していたと思います。そんなWinnyが残した功績と金子さんが逮捕されたことは、後の日本のIT開発現場に大きな影響を与えました。
Winnyは中央サーバを介さずに、個人間のコンピュータを通してファイルのやり取りができる「P2P」という仕組みを用いたソフトでした。これがとても素晴らしい技術だったことは間違いありません。
Winny以前にも、「Gnutella(グヌーテラ)」など似たようなP2Pのソフトは存在していたのですが、あくまでテスト的にみんなが面白がっているだけで実用されている感はなかった。Winnyは実用的なP2Pネットワークとしては、ほぼ初めて成立したサービスと言えます。
現在、仮想通貨に用いられているP2Pの技術は、基本的には金子さんが用いた仕組みと同じようなもので、そこにブロックチェーンという取引履歴を記録する情報を付け加えただけです。
グヌーテラもそうですが、P2Pのネットワークを作ることができるエンジニアは当時もたくさんいました。でも、金子さんは「間違ったソフトとか偽物のソフトを自動的に排除する」という、ほかにはない仕組みをWinnyに搭載させていました。
例えば、流通しているファイルの中に偽物と本物のファイルがあったとして、それを見たユーザーは偽物のファイルを削除して本物を残しておきます。すると、大量に削除されているファイルを「偽物」と判断して流通を減らす一方で、「ユーザーが多く残しているファイルはきっと本物で役に立つものだから残す」という判断をするアルゴリズムが、Winnyには実装されていたのです。
Winnyはひとつのファイルを4つに分割して、それを自分の使わないものと使うものを含めて、ある程度のバランスでデータを流通させます。それによって、人が多く使うデータほどなるべくうまく流通させていました。
つまり、アルゴリズムでバランスを取る微調整をちゃんとやっていた。これは今あるビットコインなどの仮想通貨のP2Pのシステムと比べても、非常に高度な技術なのです。
ファイル交換ソフト「Winny」の何が凄かったのか?
西村博之(にしむらひろゆき)1976年、神奈川県生まれ。東京都・赤羽に移り住み、中央大学に進学後、在学中に米国・アーカンソー州に留学。1999年に開設した「2ちゃんねる」、2005年に就任した「ニコニコ動画」の元管理人。現在は英語圏最大の掲示板サイト「4chan」の管理人を務め、フランスに在住。たまに日本にいる。週刊SPA!で10年以上連載を担当。新刊『賢い人が自然とやっている ズルい言いまわし』
記事一覧へ
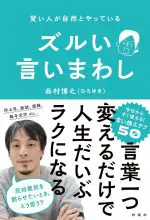 | 『賢い人が自然とやっている ズルい言いまわし』 仕事やプライベートで言葉に困ったとき…ひろゆきなら、こう言う! 50のシチュエーション別に超具体的な「言い換え術」を伝授。  |
 | 『ざんねんなインターネット』 日本のインターネット上で起こる様々な炎上事件や犯罪行為をどう見てきたのか? 満を持して出す、本気の「インターネット批評本」!  |
 | 『僕が親ならこう育てるね』 2ちゃんねる創設者・ひろゆき氏の新刊は“教育&子育て論” ※本の著者印税は、児童養護施設へのパソコン寄贈に充てられます。  |
記事一覧へ
【関連キーワードから記事を探す】
この記者は、他にもこんな記事を書いています





















