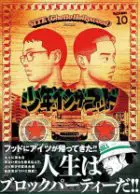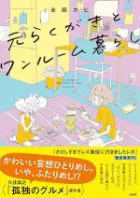秋葉原事件とは何だったのか?【中島岳志×大森立嗣】Vol.5
―[中島岳志×大森立嗣対談]―
「秋葉原無差別殺傷事件、犯人、加藤智大、彼は一体誰なのか?」― 中島岳志×大森立嗣対談 Vol.5 ― 現在、渋谷・ユーロスペースで公開中の映画『ぼっちゃん』。2008年6月8日に起こった秋葉原無差別殺傷事件を“モチーフ”にしたこの作品の公開を記念し、大森立嗣監督と、ルポ『秋葉原事件 加藤智大の軌跡』を著した中島岳志氏のふたりが、“加藤智大、秋葉原無差別殺傷事件とは何だったのか”を語りつくす。 ⇒Vol.4「加藤が生きた“斜めの関係”がない社会」
https://nikkan-spa.jp/412236 ◆「わかりやすさ」と「単純化」の違い 中島:本のエピローグでも書いたのですが、今は“わかりやすさ”と“単純化”の区別がつかなくなっています。僕がコメントを求められるときは単純化を求められる。こうだって言い切ってください、と。言い切ってくれたら、それでわかった気になって対象と自分を切り離すことができる。でもそれは対象から離れていくことなんですね。とっても。 大森:まさしくそう思います。映画でも最近、お客さんで「わからない」といって投げ出してしまう人が少なくありません。 僕はいつも思うんですが、わからないことって、知りたくならないのかな?って。僕も、最初、全然、映画がわからなかったんです。人が感動していて自分が感動できない、それがすごい悲しかったんですね。自分は心が貧しい人間なのだろうかと。それで、映画をいっぱい観ることによって、あ、こういう風に見ればいいんだと少しづつわかっていった。見方というのがあるし、感受性みたいなものは鍛えられていくものですから。 中島:「わかった」のなら、映画を撮らなくていいんですよ。たぶん。ここを間違えている映画監督の方、いるんじゃないかなってたまに思うのですが、ある真実がわかったのならば、それを言葉で短く表現できるのだったら、映画を撮る必要はない。小説もそうですが、2時間も人の物語に付き合わされるこっちの身にもなってくれと思う。 大森:中島さん、何かの対談で秋葉原事件について、「迷える99匹は政治が救うべきで、それは再分配などいろんな方法によって救える。しかし、そこからこぼれる1匹が存在する。それを救うのは文学しかない。そしてその1匹に、他の99匹もなり得る」というようなことをお話されていましたよね。僕、それを、読んで、なるほどなと。 中島:それは僕が言った言葉ではなくて、評論家・福田恆存が「一匹と九十九匹と」というエッセイで著したものです。つまり、役割の違いの話なんですよね。100人いるうちの99人を合理的に救おうとするなら政治。所得の再配分などで多くの人は救えるが、救えない1人がいる。それに手を差し伸べるのが文学だと。 だから、文学が政治になってはいけないし、政治が文学になってもいけないというのが福田恆存の言ったことで、しかも、1匹と99匹は対立するのではなくて、99匹はいつでも1匹になる存在だと。 大森:いや、「こぼれる1匹を救うのは文学しかない」というこの言葉は、モノを作る人間、僕は映画を作るわけですが、すごい元気をいただきました。 中島:問題をしっかりと合理的に書けるのならば芸術なんていらない。でも、それができないから、映画を撮ったり、小説を書いたりするだと思うんです。そこが入れ違うと、芸術が死ぬことだと思うんです。喩えるなら、宮台真司さんが言っていることを映画化してどうするんだ? みたいな話です。最近、ときどき、そういう作品がある気がします(笑)。

トークイベントの後半、加藤をモチーフとした主人公・梶友之を演じた水澤紳吾(写真右)が登壇。水澤は、「福井からの帰り、沼津に降りて風俗に行ってしまう、その気持ちはめちゃくちゃわかる。家に帰りたくない、寂しい。それが(自分の中で梶という人物像を)作るきっかけだった」と語った。また、「監督とスタッフが『違う人物として演じましょう』と言ってくださって、その言葉が僕を守ってくださったんだと思う」とも。
―[中島岳志×大森立嗣対談]―
 |
『秋葉原事件 加藤智大の軌跡』 なぜ友達がいるのに、孤独だったのか―― 
|
【関連キーワードから記事を探す】
なぜ、危ない玩具がネットで買える? 宝塚・ボウガン殺傷事件で改めて考える
名古屋デリヘル嬢の暴行致死事件。弁護人が職業べっ視発言を連発、変な空気に…
デジタル捜査のプロ、埼玉県警の敏腕刑事が刑事を辞めた理由
さいたま小四男児殺害事件が象徴する、働く母親の活躍と理想の子育ての距離/鈴木涼美
一家心中があった物件に、家族で住んでみた男の恐怖体験