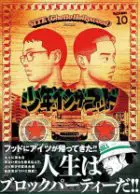映画『ドローン・オブ・ウォー』が伝える無人暗殺機の恐怖。「標的の近くにいる民間人の巻き添えは仕方がない」
村のテントで1日の仕事を終えて談笑していた村人たちがドローンのミサイル攻撃でバラバラに砕け散る――。
なぜこんな悲劇が起こるのか? 秘密作戦を指揮するCIAが「テロリストが潜んでいる建物の中に34人の民間人がいたら、35人もろとも殺してしまえばいい」と考えているからだ。
そんな軍用ドローンによる対テロ戦争の恐るべき実態に迫った映画が10月1日から公開される。
イーサン・ホーク主演の「ドローン・オブ・ウォー」だ。
 ◆「これは戦争犯罪じゃないの?」
米空軍のトミー・イーガン少佐(イーサン・ホーク)は、有人戦闘機F16の元パイロットで、今はアフガニスタンなどの紛争地域を飛行する軍用ドローンのパイロットをやっている。ただし、仕事場はラスベガスの空軍基地内のエアコンが効いたコンテナ。1万km以上離れた地球の反対側にいる標的を、遠隔操作でモニター越しに監視したり、攻撃したりするのである。
上官のジョンズ中佐(ブルース・グリーンウッド)の指示の下、ミサイルを誘導するレーザー照射担当の新人スアレス(ゾーイ・クラヴィッツ)がイスラム武装組織「タリバン」のメンバーなどの標的を捕捉し、パイロットのトミーがジョイスティックの発射ボタンをカチッと押すだけ。
無音のモニターには、10秒後に着弾する様子が映し出され、凄まじい爆発による砂ぼこりが収まると、全身や手足を吹き飛ばされた死体が転がるばかり……。
まさに「戦争ゲーム」の世界だ。
しかし、“ラングレー”というコードネームを名乗るCIA主導の「テロリスト掃討作戦」への参加を命じられると状況は一変する。
それまでの「標的の近くにいる民間人を巻き添えにしない」から「民間人の巻き添えは仕方がない」という交戦規定に変更されたのだ。「タリバン」の幹部を殺害する任務で、トミーは“ラングレー”から家族もろともミサイルで吹き飛ばせと言われ、着弾後に救助のために集まって来た人々(!)目がけて再度ミサイルを撃ち込むことを余儀なくされる。
スアレスはあまりの不愉快さに、思わず「これは戦争犯罪じゃないの?」と口にする。
この「何でもあり」の交戦規定は、「識別特性爆撃」(signature strikes)と呼ばれるものだ。要するに、「テロリストっぽい行動パターン」の者はすべて標的とみなしても構わないという事実上の規制緩和で、数人の男が軍事訓練に見えるような体操をしていたらCIAに殺されるというジョークが囁かれるほど曖昧な基準なのだ。
ジャーナリストのジェレミー・スケイヒルは、米軍情報部関係の情報提供者の「標的が潜んでいる建物のなかに三十四人の民間人がいたとしたら、三十五人もろとも殺してしまえばいい。彼らはそう考えているんだ」(『アメリカの卑劣な戦争 無人機と特殊作戦部隊の暗躍』〈上〉、横山啓明訳、柏書房)との発言を取り上げ、CIA、大統領直属の特殊作戦群、民間軍事会社が絡んだ軍用ドローンによるやりたい放題の「極秘任務」の内幕を暴いた。当然、その肝心の標的すら本当にテロリストかどうか定かでないケースもあるという。
トミーは、精神的なダメージから不眠症となり、酒に溺れ、夫婦生活にも亀裂が入るようになる。
◆高画質の映像で自分が殺した死体を目撃
もともと、軍用ドローンの評価が定着したきっかけは、暗殺作戦ではなく救出作戦における活躍だった。
リチャード・ウィッテル『無人暗殺機 ドローンの誕生』(赤根洋子訳、文藝春秋)で、「タリバン」兵士に包囲されて絶体絶命の状態だった特殊部隊員たちが、ドローンのミサイル攻撃のおかげでピンチを切り抜けたエピソードを披露している。現場の兵士たちにとってはそれが「真の無人機革命」だったと。それ以降、ドローンは人間に代わって危険地帯に入る「人助け」の役割を担うこととなったが、CIAなどの暗殺作戦で濫用されるようになると「殺人機」のイメージが強くなった。
この辺りの経緯については、劇中では、現場における上官やトミーたちの困惑という形で分かりやすく説明している。
トミーたちの苦悩をよそに、他のパイロットらは「米国本土への攻撃を防ぐためにはやむを得ない」と主張する。だがその台詞もどこか空々しい。 なぜなら、彼らもまた目の前で女性や子どもを誤爆したり、あえて巻き添えにする任務を遂行してきたからだ。高画質の映像で自らの行為の結果である死体や重傷者を目撃しなければならず、終業後はすぐに家族や恋人との日常生活に意識を戻さなければならない。現に兵士の多くがこのストレスのために離職していく。
米国は、この狂気じみた任務をずっと現場の兵士たちに押し付けてきたのである。
そもそも「テロとの戦い」とは何なのか? 果たして標的とされる人々は米国にとって本当に脅威なのか?
トミーがラストに見せる思い切った行動は、米国に対する疑問を突き付けている。
とはいえ、それは決してテクノロジーのせいではない。運用方法を決定する側にいる人間たちのモラルの問題なのだ。
だからリチャード・ウィッテルは言う。
「無人機技術はすでに人間の死に方を変えた。それはいつか、人間の生き方を変えるかもしれない」(前掲書)と。
最新の戦争と死に方について実に示唆の多い映画となっている。ぜひ劇場でそれを考えてほしい。 <文/真鍋 厚>
◆「これは戦争犯罪じゃないの?」
米空軍のトミー・イーガン少佐(イーサン・ホーク)は、有人戦闘機F16の元パイロットで、今はアフガニスタンなどの紛争地域を飛行する軍用ドローンのパイロットをやっている。ただし、仕事場はラスベガスの空軍基地内のエアコンが効いたコンテナ。1万km以上離れた地球の反対側にいる標的を、遠隔操作でモニター越しに監視したり、攻撃したりするのである。
上官のジョンズ中佐(ブルース・グリーンウッド)の指示の下、ミサイルを誘導するレーザー照射担当の新人スアレス(ゾーイ・クラヴィッツ)がイスラム武装組織「タリバン」のメンバーなどの標的を捕捉し、パイロットのトミーがジョイスティックの発射ボタンをカチッと押すだけ。
無音のモニターには、10秒後に着弾する様子が映し出され、凄まじい爆発による砂ぼこりが収まると、全身や手足を吹き飛ばされた死体が転がるばかり……。
まさに「戦争ゲーム」の世界だ。
しかし、“ラングレー”というコードネームを名乗るCIA主導の「テロリスト掃討作戦」への参加を命じられると状況は一変する。
それまでの「標的の近くにいる民間人を巻き添えにしない」から「民間人の巻き添えは仕方がない」という交戦規定に変更されたのだ。「タリバン」の幹部を殺害する任務で、トミーは“ラングレー”から家族もろともミサイルで吹き飛ばせと言われ、着弾後に救助のために集まって来た人々(!)目がけて再度ミサイルを撃ち込むことを余儀なくされる。
スアレスはあまりの不愉快さに、思わず「これは戦争犯罪じゃないの?」と口にする。
この「何でもあり」の交戦規定は、「識別特性爆撃」(signature strikes)と呼ばれるものだ。要するに、「テロリストっぽい行動パターン」の者はすべて標的とみなしても構わないという事実上の規制緩和で、数人の男が軍事訓練に見えるような体操をしていたらCIAに殺されるというジョークが囁かれるほど曖昧な基準なのだ。
ジャーナリストのジェレミー・スケイヒルは、米軍情報部関係の情報提供者の「標的が潜んでいる建物のなかに三十四人の民間人がいたとしたら、三十五人もろとも殺してしまえばいい。彼らはそう考えているんだ」(『アメリカの卑劣な戦争 無人機と特殊作戦部隊の暗躍』〈上〉、横山啓明訳、柏書房)との発言を取り上げ、CIA、大統領直属の特殊作戦群、民間軍事会社が絡んだ軍用ドローンによるやりたい放題の「極秘任務」の内幕を暴いた。当然、その肝心の標的すら本当にテロリストかどうか定かでないケースもあるという。
トミーは、精神的なダメージから不眠症となり、酒に溺れ、夫婦生活にも亀裂が入るようになる。
◆高画質の映像で自分が殺した死体を目撃
もともと、軍用ドローンの評価が定着したきっかけは、暗殺作戦ではなく救出作戦における活躍だった。
リチャード・ウィッテル『無人暗殺機 ドローンの誕生』(赤根洋子訳、文藝春秋)で、「タリバン」兵士に包囲されて絶体絶命の状態だった特殊部隊員たちが、ドローンのミサイル攻撃のおかげでピンチを切り抜けたエピソードを披露している。現場の兵士たちにとってはそれが「真の無人機革命」だったと。それ以降、ドローンは人間に代わって危険地帯に入る「人助け」の役割を担うこととなったが、CIAなどの暗殺作戦で濫用されるようになると「殺人機」のイメージが強くなった。
この辺りの経緯については、劇中では、現場における上官やトミーたちの困惑という形で分かりやすく説明している。
トミーたちの苦悩をよそに、他のパイロットらは「米国本土への攻撃を防ぐためにはやむを得ない」と主張する。だがその台詞もどこか空々しい。 なぜなら、彼らもまた目の前で女性や子どもを誤爆したり、あえて巻き添えにする任務を遂行してきたからだ。高画質の映像で自らの行為の結果である死体や重傷者を目撃しなければならず、終業後はすぐに家族や恋人との日常生活に意識を戻さなければならない。現に兵士の多くがこのストレスのために離職していく。
米国は、この狂気じみた任務をずっと現場の兵士たちに押し付けてきたのである。
そもそも「テロとの戦い」とは何なのか? 果たして標的とされる人々は米国にとって本当に脅威なのか?
トミーがラストに見せる思い切った行動は、米国に対する疑問を突き付けている。
とはいえ、それは決してテクノロジーのせいではない。運用方法を決定する側にいる人間たちのモラルの問題なのだ。
だからリチャード・ウィッテルは言う。
「無人機技術はすでに人間の死に方を変えた。それはいつか、人間の生き方を変えるかもしれない」(前掲書)と。
最新の戦争と死に方について実に示唆の多い映画となっている。ぜひ劇場でそれを考えてほしい。 <文/真鍋 厚>
 ◆「これは戦争犯罪じゃないの?」
米空軍のトミー・イーガン少佐(イーサン・ホーク)は、有人戦闘機F16の元パイロットで、今はアフガニスタンなどの紛争地域を飛行する軍用ドローンのパイロットをやっている。ただし、仕事場はラスベガスの空軍基地内のエアコンが効いたコンテナ。1万km以上離れた地球の反対側にいる標的を、遠隔操作でモニター越しに監視したり、攻撃したりするのである。
上官のジョンズ中佐(ブルース・グリーンウッド)の指示の下、ミサイルを誘導するレーザー照射担当の新人スアレス(ゾーイ・クラヴィッツ)がイスラム武装組織「タリバン」のメンバーなどの標的を捕捉し、パイロットのトミーがジョイスティックの発射ボタンをカチッと押すだけ。
無音のモニターには、10秒後に着弾する様子が映し出され、凄まじい爆発による砂ぼこりが収まると、全身や手足を吹き飛ばされた死体が転がるばかり……。
まさに「戦争ゲーム」の世界だ。
しかし、“ラングレー”というコードネームを名乗るCIA主導の「テロリスト掃討作戦」への参加を命じられると状況は一変する。
それまでの「標的の近くにいる民間人を巻き添えにしない」から「民間人の巻き添えは仕方がない」という交戦規定に変更されたのだ。「タリバン」の幹部を殺害する任務で、トミーは“ラングレー”から家族もろともミサイルで吹き飛ばせと言われ、着弾後に救助のために集まって来た人々(!)目がけて再度ミサイルを撃ち込むことを余儀なくされる。
スアレスはあまりの不愉快さに、思わず「これは戦争犯罪じゃないの?」と口にする。
この「何でもあり」の交戦規定は、「識別特性爆撃」(signature strikes)と呼ばれるものだ。要するに、「テロリストっぽい行動パターン」の者はすべて標的とみなしても構わないという事実上の規制緩和で、数人の男が軍事訓練に見えるような体操をしていたらCIAに殺されるというジョークが囁かれるほど曖昧な基準なのだ。
ジャーナリストのジェレミー・スケイヒルは、米軍情報部関係の情報提供者の「標的が潜んでいる建物のなかに三十四人の民間人がいたとしたら、三十五人もろとも殺してしまえばいい。彼らはそう考えているんだ」(『アメリカの卑劣な戦争 無人機と特殊作戦部隊の暗躍』〈上〉、横山啓明訳、柏書房)との発言を取り上げ、CIA、大統領直属の特殊作戦群、民間軍事会社が絡んだ軍用ドローンによるやりたい放題の「極秘任務」の内幕を暴いた。当然、その肝心の標的すら本当にテロリストかどうか定かでないケースもあるという。
トミーは、精神的なダメージから不眠症となり、酒に溺れ、夫婦生活にも亀裂が入るようになる。
◆高画質の映像で自分が殺した死体を目撃
もともと、軍用ドローンの評価が定着したきっかけは、暗殺作戦ではなく救出作戦における活躍だった。
リチャード・ウィッテル『無人暗殺機 ドローンの誕生』(赤根洋子訳、文藝春秋)で、「タリバン」兵士に包囲されて絶体絶命の状態だった特殊部隊員たちが、ドローンのミサイル攻撃のおかげでピンチを切り抜けたエピソードを披露している。現場の兵士たちにとってはそれが「真の無人機革命」だったと。それ以降、ドローンは人間に代わって危険地帯に入る「人助け」の役割を担うこととなったが、CIAなどの暗殺作戦で濫用されるようになると「殺人機」のイメージが強くなった。
この辺りの経緯については、劇中では、現場における上官やトミーたちの困惑という形で分かりやすく説明している。
トミーたちの苦悩をよそに、他のパイロットらは「米国本土への攻撃を防ぐためにはやむを得ない」と主張する。だがその台詞もどこか空々しい。 なぜなら、彼らもまた目の前で女性や子どもを誤爆したり、あえて巻き添えにする任務を遂行してきたからだ。高画質の映像で自らの行為の結果である死体や重傷者を目撃しなければならず、終業後はすぐに家族や恋人との日常生活に意識を戻さなければならない。現に兵士の多くがこのストレスのために離職していく。
米国は、この狂気じみた任務をずっと現場の兵士たちに押し付けてきたのである。
そもそも「テロとの戦い」とは何なのか? 果たして標的とされる人々は米国にとって本当に脅威なのか?
トミーがラストに見せる思い切った行動は、米国に対する疑問を突き付けている。
とはいえ、それは決してテクノロジーのせいではない。運用方法を決定する側にいる人間たちのモラルの問題なのだ。
だからリチャード・ウィッテルは言う。
「無人機技術はすでに人間の死に方を変えた。それはいつか、人間の生き方を変えるかもしれない」(前掲書)と。
最新の戦争と死に方について実に示唆の多い映画となっている。ぜひ劇場でそれを考えてほしい。 <文/真鍋 厚>
◆「これは戦争犯罪じゃないの?」
米空軍のトミー・イーガン少佐(イーサン・ホーク)は、有人戦闘機F16の元パイロットで、今はアフガニスタンなどの紛争地域を飛行する軍用ドローンのパイロットをやっている。ただし、仕事場はラスベガスの空軍基地内のエアコンが効いたコンテナ。1万km以上離れた地球の反対側にいる標的を、遠隔操作でモニター越しに監視したり、攻撃したりするのである。
上官のジョンズ中佐(ブルース・グリーンウッド)の指示の下、ミサイルを誘導するレーザー照射担当の新人スアレス(ゾーイ・クラヴィッツ)がイスラム武装組織「タリバン」のメンバーなどの標的を捕捉し、パイロットのトミーがジョイスティックの発射ボタンをカチッと押すだけ。
無音のモニターには、10秒後に着弾する様子が映し出され、凄まじい爆発による砂ぼこりが収まると、全身や手足を吹き飛ばされた死体が転がるばかり……。
まさに「戦争ゲーム」の世界だ。
しかし、“ラングレー”というコードネームを名乗るCIA主導の「テロリスト掃討作戦」への参加を命じられると状況は一変する。
それまでの「標的の近くにいる民間人を巻き添えにしない」から「民間人の巻き添えは仕方がない」という交戦規定に変更されたのだ。「タリバン」の幹部を殺害する任務で、トミーは“ラングレー”から家族もろともミサイルで吹き飛ばせと言われ、着弾後に救助のために集まって来た人々(!)目がけて再度ミサイルを撃ち込むことを余儀なくされる。
スアレスはあまりの不愉快さに、思わず「これは戦争犯罪じゃないの?」と口にする。
この「何でもあり」の交戦規定は、「識別特性爆撃」(signature strikes)と呼ばれるものだ。要するに、「テロリストっぽい行動パターン」の者はすべて標的とみなしても構わないという事実上の規制緩和で、数人の男が軍事訓練に見えるような体操をしていたらCIAに殺されるというジョークが囁かれるほど曖昧な基準なのだ。
ジャーナリストのジェレミー・スケイヒルは、米軍情報部関係の情報提供者の「標的が潜んでいる建物のなかに三十四人の民間人がいたとしたら、三十五人もろとも殺してしまえばいい。彼らはそう考えているんだ」(『アメリカの卑劣な戦争 無人機と特殊作戦部隊の暗躍』〈上〉、横山啓明訳、柏書房)との発言を取り上げ、CIA、大統領直属の特殊作戦群、民間軍事会社が絡んだ軍用ドローンによるやりたい放題の「極秘任務」の内幕を暴いた。当然、その肝心の標的すら本当にテロリストかどうか定かでないケースもあるという。
トミーは、精神的なダメージから不眠症となり、酒に溺れ、夫婦生活にも亀裂が入るようになる。
◆高画質の映像で自分が殺した死体を目撃
もともと、軍用ドローンの評価が定着したきっかけは、暗殺作戦ではなく救出作戦における活躍だった。
リチャード・ウィッテル『無人暗殺機 ドローンの誕生』(赤根洋子訳、文藝春秋)で、「タリバン」兵士に包囲されて絶体絶命の状態だった特殊部隊員たちが、ドローンのミサイル攻撃のおかげでピンチを切り抜けたエピソードを披露している。現場の兵士たちにとってはそれが「真の無人機革命」だったと。それ以降、ドローンは人間に代わって危険地帯に入る「人助け」の役割を担うこととなったが、CIAなどの暗殺作戦で濫用されるようになると「殺人機」のイメージが強くなった。
この辺りの経緯については、劇中では、現場における上官やトミーたちの困惑という形で分かりやすく説明している。
トミーたちの苦悩をよそに、他のパイロットらは「米国本土への攻撃を防ぐためにはやむを得ない」と主張する。だがその台詞もどこか空々しい。 なぜなら、彼らもまた目の前で女性や子どもを誤爆したり、あえて巻き添えにする任務を遂行してきたからだ。高画質の映像で自らの行為の結果である死体や重傷者を目撃しなければならず、終業後はすぐに家族や恋人との日常生活に意識を戻さなければならない。現に兵士の多くがこのストレスのために離職していく。
米国は、この狂気じみた任務をずっと現場の兵士たちに押し付けてきたのである。
そもそも「テロとの戦い」とは何なのか? 果たして標的とされる人々は米国にとって本当に脅威なのか?
トミーがラストに見せる思い切った行動は、米国に対する疑問を突き付けている。
とはいえ、それは決してテクノロジーのせいではない。運用方法を決定する側にいる人間たちのモラルの問題なのだ。
だからリチャード・ウィッテルは言う。
「無人機技術はすでに人間の死に方を変えた。それはいつか、人間の生き方を変えるかもしれない」(前掲書)と。
最新の戦争と死に方について実に示唆の多い映画となっている。ぜひ劇場でそれを考えてほしい。 <文/真鍋 厚>
 |
『テロリスト・ワールド』 なぜ、それは〈テロ〉と呼ばれるのか? 
|
【関連キーワードから記事を探す】
元モデルが“ドローン”に見出した活路「稼げるような土壌を作りたい」
ラジコンはOKなのにドローンはNGのワケ。日本のドローン規制事情
コロナ禍で需要激減のタクシー業界、それでも「勝ち組」出現の意外なワケ
ドローン最前線。規制だらけの日本では独自の工夫・改良が
“空飛ぶクルマ”を作る企業が求める人材。ラジコンマニア、自衛隊パイロットetc.
この記者は、他にもこんな記事を書いています