トランプ大統領就任で再熱!「沖縄米軍基地問題」が生まれたワケを上念司氏が解説
トランプ大統領就任によって、刻々と変わる国際情勢。その変化の波に巻き込まれているのは、日本も同様だ。
なかでも、以前から「日本は米軍の駐留経費を全額負担すべき」との発言を繰り返してきたトランプ大統領就任により、再度注目を集めているが米軍基地問題。特に沖縄の米軍基地問題については、頻繁に基地反対運動も行われるなど、社会的にも大きな争点となっている。
そこで、『保守の本懐』を出版したばかりの作家・経済評論家の上念司氏に、沖縄米軍基地問題が日本を分断する理由や問題が生まれた社会的背景などについて解説してもらった。
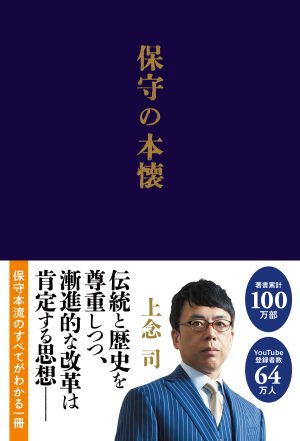 (本記事は、『保守の本懐』より一部を抜粋し、再編集しています)
(本記事は、『保守の本懐』より一部を抜粋し、再編集しています)
 ソ連崩壊後、自民党は2度にわたって政権の座から陥落します。1度目は1993年の細川連立政権の時、2度目は2009年の民主党政権の時です。共産主義者たちとの闘いに勝ったのになぜ?
理由はバブル崩壊以降の経済失政にありました。平成に入ると、それまで経済政策だけは間違えなかった自民党がことごとく悪手を打ち続けたのです。この点については拙書『経済で読み解く日本史 平成時代』(飛鳥新社)に詳しく書きましたので、ここでは簡単に説明します。
1990年から始まる土地バブルの崩壊とそれに続く不良債権問題の処理に、日本政府は13年もの年を費やしてしまったのです。
そもそも、バブル崩壊自体が大蔵省による不動産融資規制と日銀の利上げによるオーバーキルが原因でした。さらに、2003年に不良債権処理が終わった後も、物価上昇率がマイナスになるデフレは解消しませんでした。
速水優、福井俊彦、白川方明と続く日銀総裁が十分な金融緩和を行わなかったからです。そのせいで、1998年から2012年までデフレ状態は解消せず、失業が大幅に増えました。その影響を受けたのがロスジェネと呼ばれる、私より少し後輩たちの世代です。
すでに齢50に達する彼らは、学校を卒業した直後からデフレ不況が続き、ろくに就職できないまま年を取ってしまいました。この時期、日本の自殺者数はそれ以前の2万人台から3万人台に増加し、その原因の多くが経済的な問題を苦にしたものでした。
ソ連崩壊後、自民党は2度にわたって政権の座から陥落します。1度目は1993年の細川連立政権の時、2度目は2009年の民主党政権の時です。共産主義者たちとの闘いに勝ったのになぜ?
理由はバブル崩壊以降の経済失政にありました。平成に入ると、それまで経済政策だけは間違えなかった自民党がことごとく悪手を打ち続けたのです。この点については拙書『経済で読み解く日本史 平成時代』(飛鳥新社)に詳しく書きましたので、ここでは簡単に説明します。
1990年から始まる土地バブルの崩壊とそれに続く不良債権問題の処理に、日本政府は13年もの年を費やしてしまったのです。
そもそも、バブル崩壊自体が大蔵省による不動産融資規制と日銀の利上げによるオーバーキルが原因でした。さらに、2003年に不良債権処理が終わった後も、物価上昇率がマイナスになるデフレは解消しませんでした。
速水優、福井俊彦、白川方明と続く日銀総裁が十分な金融緩和を行わなかったからです。そのせいで、1998年から2012年までデフレ状態は解消せず、失業が大幅に増えました。その影響を受けたのがロスジェネと呼ばれる、私より少し後輩たちの世代です。
すでに齢50に達する彼らは、学校を卒業した直後からデフレ不況が続き、ろくに就職できないまま年を取ってしまいました。この時期、日本の自殺者数はそれ以前の2万人台から3万人台に増加し、その原因の多くが経済的な問題を苦にしたものでした。
 経済的に困窮した人々は救済を求めて過激思想に走ります。革命運動はソ連崩壊で下火になっていましたが、行き場を失った共産主義者は新たな運動を開始していました。かつて日本共産党のナンバー4で参議院議員だった筆坂秀世氏は、それを「隙間産業」と名付けました。
例えば、それらは環境問題、LGBTQ、沖縄の米軍基地問題、アイヌ問題、在日朝鮮人問題、反グローバリズムなど、革命という大きなテーマに比べれば矮小で、それだけで世の中が変えられるのかと思えるようなショボい運動です。
デフレ不況時に話題になった派遣村のような活動も、ポストモダンのようなファッショナブルでナンセンスな思想運動も、隙間産業に加えていいでしょう。
これら隙間産業に共通することは、「革命は起こせないけど、現状の批判はする」という点です。
例えば、資本主義の暴走が地球環境を破壊しているとか、今の政府のせいでマイノリティの人権が抑圧されているといった批判です。
もちろん、こういった社会的課題は1つ1つ解決していかなければならないものもあるでしょう。
だからこそ、批判ばかりでなく建設的な議論が必要です。過去にそういう制度が決まった歴史的経緯、先人たちの議論、先行研究を踏まえた議論を着実に行っていくことが大事なのではないでしょうか?
経済的に困窮した人々は救済を求めて過激思想に走ります。革命運動はソ連崩壊で下火になっていましたが、行き場を失った共産主義者は新たな運動を開始していました。かつて日本共産党のナンバー4で参議院議員だった筆坂秀世氏は、それを「隙間産業」と名付けました。
例えば、それらは環境問題、LGBTQ、沖縄の米軍基地問題、アイヌ問題、在日朝鮮人問題、反グローバリズムなど、革命という大きなテーマに比べれば矮小で、それだけで世の中が変えられるのかと思えるようなショボい運動です。
デフレ不況時に話題になった派遣村のような活動も、ポストモダンのようなファッショナブルでナンセンスな思想運動も、隙間産業に加えていいでしょう。
これら隙間産業に共通することは、「革命は起こせないけど、現状の批判はする」という点です。
例えば、資本主義の暴走が地球環境を破壊しているとか、今の政府のせいでマイノリティの人権が抑圧されているといった批判です。
もちろん、こういった社会的課題は1つ1つ解決していかなければならないものもあるでしょう。
だからこそ、批判ばかりでなく建設的な議論が必要です。過去にそういう制度が決まった歴史的経緯、先人たちの議論、先行研究を踏まえた議論を着実に行っていくことが大事なのではないでしょうか?
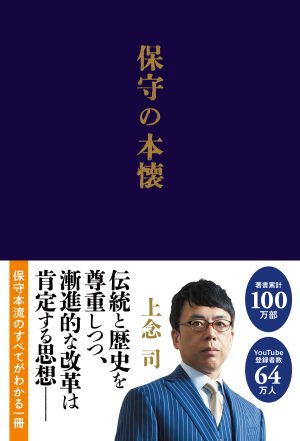
『保守の本懐』上念司(著)
「隙間産業」に目を付けた共産主義者たち

※写真はイメージです(以下同)
「革命は起こせないけど、現状の批判はする」隙間産業
 経済的に困窮した人々は救済を求めて過激思想に走ります。革命運動はソ連崩壊で下火になっていましたが、行き場を失った共産主義者は新たな運動を開始していました。かつて日本共産党のナンバー4で参議院議員だった筆坂秀世氏は、それを「隙間産業」と名付けました。
例えば、それらは環境問題、LGBTQ、沖縄の米軍基地問題、アイヌ問題、在日朝鮮人問題、反グローバリズムなど、革命という大きなテーマに比べれば矮小で、それだけで世の中が変えられるのかと思えるようなショボい運動です。
デフレ不況時に話題になった派遣村のような活動も、ポストモダンのようなファッショナブルでナンセンスな思想運動も、隙間産業に加えていいでしょう。
これら隙間産業に共通することは、「革命は起こせないけど、現状の批判はする」という点です。
例えば、資本主義の暴走が地球環境を破壊しているとか、今の政府のせいでマイノリティの人権が抑圧されているといった批判です。
もちろん、こういった社会的課題は1つ1つ解決していかなければならないものもあるでしょう。
だからこそ、批判ばかりでなく建設的な議論が必要です。過去にそういう制度が決まった歴史的経緯、先人たちの議論、先行研究を踏まえた議論を着実に行っていくことが大事なのではないでしょうか?
経済的に困窮した人々は救済を求めて過激思想に走ります。革命運動はソ連崩壊で下火になっていましたが、行き場を失った共産主義者は新たな運動を開始していました。かつて日本共産党のナンバー4で参議院議員だった筆坂秀世氏は、それを「隙間産業」と名付けました。
例えば、それらは環境問題、LGBTQ、沖縄の米軍基地問題、アイヌ問題、在日朝鮮人問題、反グローバリズムなど、革命という大きなテーマに比べれば矮小で、それだけで世の中が変えられるのかと思えるようなショボい運動です。
デフレ不況時に話題になった派遣村のような活動も、ポストモダンのようなファッショナブルでナンセンスな思想運動も、隙間産業に加えていいでしょう。
これら隙間産業に共通することは、「革命は起こせないけど、現状の批判はする」という点です。
例えば、資本主義の暴走が地球環境を破壊しているとか、今の政府のせいでマイノリティの人権が抑圧されているといった批判です。
もちろん、こういった社会的課題は1つ1つ解決していかなければならないものもあるでしょう。
だからこそ、批判ばかりでなく建設的な議論が必要です。過去にそういう制度が決まった歴史的経緯、先人たちの議論、先行研究を踏まえた議論を着実に行っていくことが大事なのではないでしょうか?
1
2
1969年、東京都生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。在学中は創立1901年の日本最古の弁論部・辞達学会に所属。日本長期信用銀行、臨海セミナーを経て独立。2007年、経済評論家・勝間和代氏と株式会社「監査と分析」を設立。取締役・共同事業パートナーに就任(現在は代表取締役)。2010年、米国イェール大学経済学部の浜田宏一教授に師事し、薫陶を受ける。金融、財政、外交、防衛問題に精通し、積極的な評論、著述活動を展開している。
記事一覧へ
記事一覧へ

|
『保守の本懐』 保守本流のすべてがわかる一冊 

|
【関連キーワードから記事を探す】
この記者は、他にもこんな記事を書いています




















