日本国憲法によって日本の伝統は“リセット”された? 上念司氏が語る教科書に載らない戦後史
敗戦を迎えて80年。戦後の占領政策の最中、実は天皇制や国の枠組みを解体しようという動きがGHQ内部にあった事をご存じだろうか。
仮にその試みが実現していた場合は、冷戦初期のアジアにおける地政学的な勢力図は大きく変わっていたはずだと指摘するのは、『保守の本懐』を上梓したばかりの作家で経済評論家の上念司氏だ。そんな上念氏が解説する、教科書には載らない「もうひとつの戦後史」とは――。
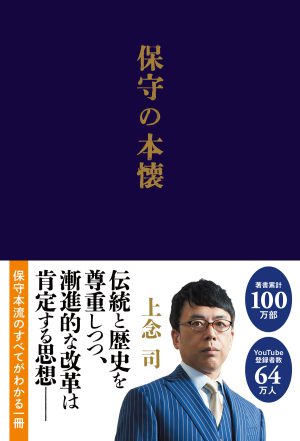 (本記事は、『保守の本懐』より一部を抜粋し、再編集しています)
(本記事は、『保守の本懐』より一部を抜粋し、再編集しています)
 対米開戦からの大東亜戦争。日本はこの一世一代の大ギャンブルに失敗し、敗北しました。その結果、日本は重い十字架を背負わされてしまいました。ポツダム宣言を受諾する唯一の条件として日本政府が提示したのは國體護持。
しかし、占領軍の中には、その約束を反故にしようとする勢力がいました。トーマス・アーサー・ビッソンやエドガートン・ハーバート・ノーマンなど、GHQ(連合国軍総司令部)に所属していたアメリカ人の一部はソ連の同調者だったのです。
彼らは、天皇を戦犯として裁き、憲法を改編し、日本の國體そのものを変えようと企んでいました。これは1995年に公開されたヴェノナ文書の研究で明らかになるのですが、もちろんそんなのは後の祭りです。
しかし、この困難な状況の中で、憲法大臣の金森徳次郎をはじめとした「愛国者」たちは國體護持に尽力しました。
その結果、大日本帝国憲法第1条から第7条と同じく、日本国憲法でも「第一章 天皇(第1条から第8条)」と置き、立憲民主制の形を維持し、その内容をもってGHQを説得することに成功したのです。
文体は違えど、統治権の所在以外は基本的に書いてあることは同じです。例えば、「天皇は神聖にして犯すべからず」とは、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と意図するところは同じでしょ?
対米開戦からの大東亜戦争。日本はこの一世一代の大ギャンブルに失敗し、敗北しました。その結果、日本は重い十字架を背負わされてしまいました。ポツダム宣言を受諾する唯一の条件として日本政府が提示したのは國體護持。
しかし、占領軍の中には、その約束を反故にしようとする勢力がいました。トーマス・アーサー・ビッソンやエドガートン・ハーバート・ノーマンなど、GHQ(連合国軍総司令部)に所属していたアメリカ人の一部はソ連の同調者だったのです。
彼らは、天皇を戦犯として裁き、憲法を改編し、日本の國體そのものを変えようと企んでいました。これは1995年に公開されたヴェノナ文書の研究で明らかになるのですが、もちろんそんなのは後の祭りです。
しかし、この困難な状況の中で、憲法大臣の金森徳次郎をはじめとした「愛国者」たちは國體護持に尽力しました。
その結果、大日本帝国憲法第1条から第7条と同じく、日本国憲法でも「第一章 天皇(第1条から第8条)」と置き、立憲民主制の形を維持し、その内容をもってGHQを説得することに成功したのです。
文体は違えど、統治権の所在以外は基本的に書いてあることは同じです。例えば、「天皇は神聖にして犯すべからず」とは、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と意図するところは同じでしょ?
 そもそも1000年以上前に政治権力を失い、その後は国民のために祈り続ける天皇という存在が、国民の総意なしに存続しようがありません。
憲法の条文上も天皇と民の関係(君民共治)は守られました。また、手続きの面では、日本国憲法はあくまで大日本帝国憲法の改正手続きに則って成立しています。
さらに、憲法の条文だけでなく、実際の天皇と民の関係にも変化はありませんでした。皇居の一般参賀などの状況を見れば、いまだに日本人の大多数が皇室と天皇陛下に敬意を払っていることが分かります。
平成31年、明仁天皇最後の一般参賀に普段の2倍の16万人もの国民が集まったことはまさにその証左と言えるでしょう。
そもそも1000年以上前に政治権力を失い、その後は国民のために祈り続ける天皇という存在が、国民の総意なしに存続しようがありません。
憲法の条文上も天皇と民の関係(君民共治)は守られました。また、手続きの面では、日本国憲法はあくまで大日本帝国憲法の改正手続きに則って成立しています。
さらに、憲法の条文だけでなく、実際の天皇と民の関係にも変化はありませんでした。皇居の一般参賀などの状況を見れば、いまだに日本人の大多数が皇室と天皇陛下に敬意を払っていることが分かります。
平成31年、明仁天皇最後の一般参賀に普段の2倍の16万人もの国民が集まったことはまさにその証左と言えるでしょう。
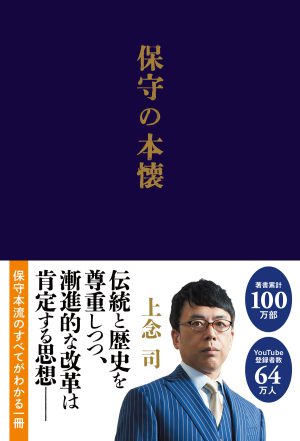
『保守の本懐』上念司(著)
憲法改正後、天皇の存在はどう変わったのか

※写真はイメージです(以下同)
はるか昔から続く日本人の皇室と天皇陛下への敬意
 そもそも1000年以上前に政治権力を失い、その後は国民のために祈り続ける天皇という存在が、国民の総意なしに存続しようがありません。
憲法の条文上も天皇と民の関係(君民共治)は守られました。また、手続きの面では、日本国憲法はあくまで大日本帝国憲法の改正手続きに則って成立しています。
さらに、憲法の条文だけでなく、実際の天皇と民の関係にも変化はありませんでした。皇居の一般参賀などの状況を見れば、いまだに日本人の大多数が皇室と天皇陛下に敬意を払っていることが分かります。
平成31年、明仁天皇最後の一般参賀に普段の2倍の16万人もの国民が集まったことはまさにその証左と言えるでしょう。
そもそも1000年以上前に政治権力を失い、その後は国民のために祈り続ける天皇という存在が、国民の総意なしに存続しようがありません。
憲法の条文上も天皇と民の関係(君民共治)は守られました。また、手続きの面では、日本国憲法はあくまで大日本帝国憲法の改正手続きに則って成立しています。
さらに、憲法の条文だけでなく、実際の天皇と民の関係にも変化はありませんでした。皇居の一般参賀などの状況を見れば、いまだに日本人の大多数が皇室と天皇陛下に敬意を払っていることが分かります。
平成31年、明仁天皇最後の一般参賀に普段の2倍の16万人もの国民が集まったことはまさにその証左と言えるでしょう。
1969年、東京都生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。在学中は創立1901年の日本最古の弁論部・辞達学会に所属。日本長期信用銀行、臨海セミナーを経て独立。2007年、経済評論家・勝間和代氏と株式会社「監査と分析」を設立。取締役・共同事業パートナーに就任(現在は代表取締役)。2010年、米国イェール大学経済学部の浜田宏一教授に師事し、薫陶を受ける。金融、財政、外交、防衛問題に精通し、積極的な評論、著述活動を展開している。
記事一覧へ
記事一覧へ

|
『保守の本懐』 保守本流のすべてがわかる一冊 

|
【関連キーワードから記事を探す】
日本国憲法によって日本の伝統は“リセット”された? 上念司氏が語る教科書に載らない戦後史
常に不安定な「皇位継承の伝統」をいかに守るか/倉山満
反論できない皇族をサンドバッグのように扱う人々の卑劣さ/倉山満
天皇や皇族は奴隷ではない。権限がないことと自由や人権がないことは違う/倉山満
特別な祝日「天皇誕生日」について調べてみた
この記者は、他にもこんな記事を書いています




















