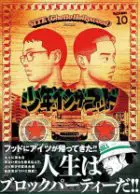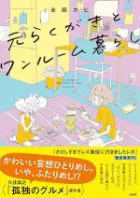昭和は本当に良い時代だったのか?【環境問題編】
「人々は活気に溢れていた」「温かい時代だった」『ALWAYS 三丁目の夕日』第3弾も公開され、ますますブーム沸騰中の「昭和」にもの申す! 過去を懐かしむことは決して悪いことではない。しかし、昭和ノスタル爺の懐かしみ方は常軌を逸している。昭和は本当に良かった時代なのか!? “昭和ブーム”の浅薄さを検証し、その後ろ向きな懐古主義がもたらす弊害について考えてみた。
 【昭和懐古主義派の主張】
◆都内でも自然が残って、山里も綺麗だった……。とても生きやすい時代だった
昭和ノスタルジーで語られる生活環境といえば、まだ雑木林や原っぱ、あるいはザリガニ釣りをするような池や川が残っていたというもの。都心部でも、空気はそれほど汚れておらず、夕日や星空が綺麗に見えるなど、都市化と自然がまだ調和していたというが、スクリーンではわからぬものもあるのでは!?
【実際は……】
◆環境に対する意識が希薄で汚物も有害物質もタレ流し
映画『ALWAYS 三丁目の夕日』の舞台は昭和30年代だが、当時の社会状況を検証した『昭和33年』(ちくま新書)の著者・布施克彦氏は次のように語る。
「映画『ALWAYS』では大通りを走っている自動車の数が少なすぎますね」(布施氏)というように、当時すでに新聞でも排ガス汚染や騒音が問題になっていた。また、現在と比べれば都内にも自然は残っていたが、建設ラッシュの都内では、「建設現場も雑で、騒音や振動など周辺対策は考慮されていなかった」のだ。
環境対策という概念すらなかったため、アスベストもガンガン使われていたわけだ。
さらに、下水道の整備はまったく遅れていたので、都内を流れる川には生活排水が流れ込み、急激にドブ川と化していた。映像ではニオイは一切伝わらないが、川周辺の地域では、特に夏場などは猛烈な悪臭に悩まされていたという。
ついでに言えば、公共マナーの概念も薄いから、そこら中でタバコのポイ捨てはするわ、タンは吐くわで、街がかなり汚れていた。
さらに深刻な問題としては「水俣病」や「四日市ぜんそく」など、全国的に公害病が次々に発生していたが、経済成長最優先だった日本では、政府も環境対策は二の次で、長らく放置されたままだった。
医療環境や衛生面も現在とは比べものにならず、昭和33年の平均寿命は男が約65歳、女が約70歳で、今と比べて15年も短い。また乳幼児死亡率は1000人当たり34・5人と、今の10倍以上あり、映画やテーマパークの書き割りでは伝わらない健康や生命へのリスクが溢れる時代だったのだ。
【布施克彦氏】
’47年、東京都生まれ。総合商社やメーカー勤務を経て、著作活動に入る。『昭和33年』、『元商社マンが発見した古代の商人たち』など著書多数
イラスト/テラムラリョウ
― [昭和ノスタルジー]が日本を滅ぼす【1】 ―
【昭和懐古主義派の主張】
◆都内でも自然が残って、山里も綺麗だった……。とても生きやすい時代だった
昭和ノスタルジーで語られる生活環境といえば、まだ雑木林や原っぱ、あるいはザリガニ釣りをするような池や川が残っていたというもの。都心部でも、空気はそれほど汚れておらず、夕日や星空が綺麗に見えるなど、都市化と自然がまだ調和していたというが、スクリーンではわからぬものもあるのでは!?
【実際は……】
◆環境に対する意識が希薄で汚物も有害物質もタレ流し
映画『ALWAYS 三丁目の夕日』の舞台は昭和30年代だが、当時の社会状況を検証した『昭和33年』(ちくま新書)の著者・布施克彦氏は次のように語る。
「映画『ALWAYS』では大通りを走っている自動車の数が少なすぎますね」(布施氏)というように、当時すでに新聞でも排ガス汚染や騒音が問題になっていた。また、現在と比べれば都内にも自然は残っていたが、建設ラッシュの都内では、「建設現場も雑で、騒音や振動など周辺対策は考慮されていなかった」のだ。
環境対策という概念すらなかったため、アスベストもガンガン使われていたわけだ。
さらに、下水道の整備はまったく遅れていたので、都内を流れる川には生活排水が流れ込み、急激にドブ川と化していた。映像ではニオイは一切伝わらないが、川周辺の地域では、特に夏場などは猛烈な悪臭に悩まされていたという。
ついでに言えば、公共マナーの概念も薄いから、そこら中でタバコのポイ捨てはするわ、タンは吐くわで、街がかなり汚れていた。
さらに深刻な問題としては「水俣病」や「四日市ぜんそく」など、全国的に公害病が次々に発生していたが、経済成長最優先だった日本では、政府も環境対策は二の次で、長らく放置されたままだった。
医療環境や衛生面も現在とは比べものにならず、昭和33年の平均寿命は男が約65歳、女が約70歳で、今と比べて15年も短い。また乳幼児死亡率は1000人当たり34・5人と、今の10倍以上あり、映画やテーマパークの書き割りでは伝わらない健康や生命へのリスクが溢れる時代だったのだ。
【布施克彦氏】
’47年、東京都生まれ。総合商社やメーカー勤務を経て、著作活動に入る。『昭和33年』、『元商社マンが発見した古代の商人たち』など著書多数
イラスト/テラムラリョウ
― [昭和ノスタルジー]が日本を滅ぼす【1】 ―
 【昭和懐古主義派の主張】
◆都内でも自然が残って、山里も綺麗だった……。とても生きやすい時代だった
昭和ノスタルジーで語られる生活環境といえば、まだ雑木林や原っぱ、あるいはザリガニ釣りをするような池や川が残っていたというもの。都心部でも、空気はそれほど汚れておらず、夕日や星空が綺麗に見えるなど、都市化と自然がまだ調和していたというが、スクリーンではわからぬものもあるのでは!?
【実際は……】
◆環境に対する意識が希薄で汚物も有害物質もタレ流し
映画『ALWAYS 三丁目の夕日』の舞台は昭和30年代だが、当時の社会状況を検証した『昭和33年』(ちくま新書)の著者・布施克彦氏は次のように語る。
「映画『ALWAYS』では大通りを走っている自動車の数が少なすぎますね」(布施氏)というように、当時すでに新聞でも排ガス汚染や騒音が問題になっていた。また、現在と比べれば都内にも自然は残っていたが、建設ラッシュの都内では、「建設現場も雑で、騒音や振動など周辺対策は考慮されていなかった」のだ。
環境対策という概念すらなかったため、アスベストもガンガン使われていたわけだ。
さらに、下水道の整備はまったく遅れていたので、都内を流れる川には生活排水が流れ込み、急激にドブ川と化していた。映像ではニオイは一切伝わらないが、川周辺の地域では、特に夏場などは猛烈な悪臭に悩まされていたという。
ついでに言えば、公共マナーの概念も薄いから、そこら中でタバコのポイ捨てはするわ、タンは吐くわで、街がかなり汚れていた。
さらに深刻な問題としては「水俣病」や「四日市ぜんそく」など、全国的に公害病が次々に発生していたが、経済成長最優先だった日本では、政府も環境対策は二の次で、長らく放置されたままだった。
医療環境や衛生面も現在とは比べものにならず、昭和33年の平均寿命は男が約65歳、女が約70歳で、今と比べて15年も短い。また乳幼児死亡率は1000人当たり34・5人と、今の10倍以上あり、映画やテーマパークの書き割りでは伝わらない健康や生命へのリスクが溢れる時代だったのだ。
【布施克彦氏】
’47年、東京都生まれ。総合商社やメーカー勤務を経て、著作活動に入る。『昭和33年』、『元商社マンが発見した古代の商人たち』など著書多数
イラスト/テラムラリョウ
― [昭和ノスタルジー]が日本を滅ぼす【1】 ―
【昭和懐古主義派の主張】
◆都内でも自然が残って、山里も綺麗だった……。とても生きやすい時代だった
昭和ノスタルジーで語られる生活環境といえば、まだ雑木林や原っぱ、あるいはザリガニ釣りをするような池や川が残っていたというもの。都心部でも、空気はそれほど汚れておらず、夕日や星空が綺麗に見えるなど、都市化と自然がまだ調和していたというが、スクリーンではわからぬものもあるのでは!?
【実際は……】
◆環境に対する意識が希薄で汚物も有害物質もタレ流し
映画『ALWAYS 三丁目の夕日』の舞台は昭和30年代だが、当時の社会状況を検証した『昭和33年』(ちくま新書)の著者・布施克彦氏は次のように語る。
「映画『ALWAYS』では大通りを走っている自動車の数が少なすぎますね」(布施氏)というように、当時すでに新聞でも排ガス汚染や騒音が問題になっていた。また、現在と比べれば都内にも自然は残っていたが、建設ラッシュの都内では、「建設現場も雑で、騒音や振動など周辺対策は考慮されていなかった」のだ。
環境対策という概念すらなかったため、アスベストもガンガン使われていたわけだ。
さらに、下水道の整備はまったく遅れていたので、都内を流れる川には生活排水が流れ込み、急激にドブ川と化していた。映像ではニオイは一切伝わらないが、川周辺の地域では、特に夏場などは猛烈な悪臭に悩まされていたという。
ついでに言えば、公共マナーの概念も薄いから、そこら中でタバコのポイ捨てはするわ、タンは吐くわで、街がかなり汚れていた。
さらに深刻な問題としては「水俣病」や「四日市ぜんそく」など、全国的に公害病が次々に発生していたが、経済成長最優先だった日本では、政府も環境対策は二の次で、長らく放置されたままだった。
医療環境や衛生面も現在とは比べものにならず、昭和33年の平均寿命は男が約65歳、女が約70歳で、今と比べて15年も短い。また乳幼児死亡率は1000人当たり34・5人と、今の10倍以上あり、映画やテーマパークの書き割りでは伝わらない健康や生命へのリスクが溢れる時代だったのだ。
【布施克彦氏】
’47年、東京都生まれ。総合商社やメーカー勤務を経て、著作活動に入る。『昭和33年』、『元商社マンが発見した古代の商人たち』など著書多数
イラスト/テラムラリョウ
― [昭和ノスタルジー]が日本を滅ぼす【1】 ―
【関連キーワードから記事を探す】
「休む」を改革せよ!医学博士が教える最強の休息法5選
「病気ではないのに、体がずっとダルい人」がまずは取り入れるべき“3つの習慣”
「健康診断をサボり気味の人」のほうが長生きできる!? “正常値の維持”にメリットはない
「体重が5kg減って喜んでいたら…」元『とくダネ!』フジアナウンサーが患った“大病”の前兆
陸上自衛隊初の心理幹部が教える「強メンタル」のつくり方。感情の乱れを静める“DNA呼吸法”とは
かつて家庭の中心だったビデオテープが、もう再生できなくなる…“家に眠っている思い出”をどうすべき?
「タバコの煙が充満するバス」「選手の住所が載っていた選手名鑑」…今では考えられない昭和プロ野球の“常識”
「文化遺産」として見直される昭和の都電。「アニメの聖地」や「渋沢ゆかりの地」などに残る都電の今を追う
はるな愛、ショーパブで働く女性たちにエール「昔の自分を思い出します」
食を愛するデブが「昭和っぽさが魅力の大衆酒場」にハマってしまう理由