「もう包丁を出すしかない」死を覚悟したデスマッチファイター・竹田誠志のルーツを辿る
「いつ死んでもいい」
 「痛いのは嫌いじゃないんです。相手を痛めつけるより、自分が受けるほうがいい。そのほうがおいしいですから。リアクション芸人と同じです」
しかし、細菌に感染して熱が回り、歩行が困難になったこともある。腕の骨の手前までガラスが突き刺さり、腕を切って取り出したこともある。洗浄に1時間かかり、医師に「もうイヤ……」と泣かれた。
「いつ死んでもいいと思ってます。それくらいじゃないと、できないです」
「痛いのは嫌いじゃないんです。相手を痛めつけるより、自分が受けるほうがいい。そのほうがおいしいですから。リアクション芸人と同じです」
しかし、細菌に感染して熱が回り、歩行が困難になったこともある。腕の骨の手前までガラスが突き刺さり、腕を切って取り出したこともある。洗浄に1時間かかり、医師に「もうイヤ……」と泣かれた。
「いつ死んでもいいと思ってます。それくらいじゃないと、できないです」
 中学生のときに出会った、あのビデオを見せてもらった。
1995年3月5日、大日本プロレス旗揚げ戦。「バラ線(有刺鉄線)パーフェクト フォールデスマッチ」。白いマスクの男が、パイプ椅子で殴られ、カメラに向かって突進してくる。「あぶない……!」次の瞬間、画面いっぱいに、血の海原が広がった。
中学生のときに出会った、あのビデオを見せてもらった。
1995年3月5日、大日本プロレス旗揚げ戦。「バラ線(有刺鉄線)パーフェクト フォールデスマッチ」。白いマスクの男が、パイプ椅子で殴られ、カメラに向かって突進してくる。「あぶない……!」次の瞬間、画面いっぱいに、血の海原が広がった。
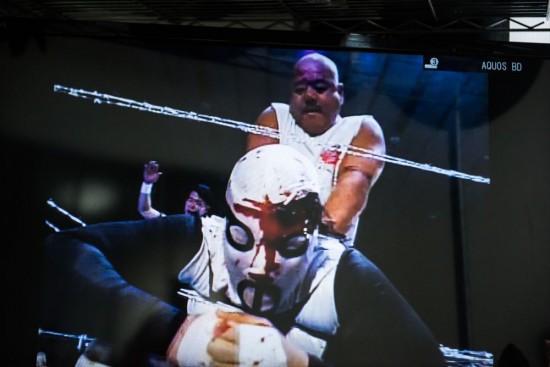 ああ、これか。この興奮を、子供の頃に味わってしまったのだ。憑りつかれるほかなかったのかもしれない。デスマッチという魍魎に――。
「アメリカのデスマッチを日本でもやってみたいです。日本はプロレスの攻防ありきですが、アメリカは凶器ありき。エグいことをやればやるほど、お客さんは喜ぶんです」
14歳のときに紛れ込んだ“非日常”。竹田はいまもずっと、その中にいる。
取材・文/尾崎ムギ子 撮影/タカハシアキラ
ああ、これか。この興奮を、子供の頃に味わってしまったのだ。憑りつかれるほかなかったのかもしれない。デスマッチという魍魎に――。
「アメリカのデスマッチを日本でもやってみたいです。日本はプロレスの攻防ありきですが、アメリカは凶器ありき。エグいことをやればやるほど、お客さんは喜ぶんです」
14歳のときに紛れ込んだ“非日常”。竹田はいまもずっと、その中にいる。
取材・文/尾崎ムギ子 撮影/タカハシアキラ
尾崎ムギ子/ライター、編集者。リクルート、編集プロダクションを経て、フリー。2015年1月、“飯伏幸太vsヨシヒコ戦”の動画をきっかけにプロレスにのめり込む。初代タイガーマスクこと佐山サトルを応援する「佐山女子会(@sayama_joshi)」発起人。Twitter:@ozaki_mugiko
1
2
【関連キーワードから記事を探す】
デスマッチファイター・葛西純。どんな凶器よりも「ゴキブリ、歯医者のほうが怖い」
デスマッチ界のカリスマからの挑戦を受ける竹田誠志「この試合が正念場。俺は2番煎じじゃない」
「もう包丁を出すしかない」死を覚悟したデスマッチファイター・竹田誠志のルーツを辿る
大仁田厚に憧れて――WWEも評価する“弾丸戦士”田中将斗がZERO1に止まる理由【最強レスラー数珠つなぎvol.8】
ジャイアント馬場のギミックから始まった――“巨神”石川修司が辿った茨道【最強レスラー数珠つなぎvol.6】
鈴木みのる、“新日”若手時代から変わらないストロングスタイル「僕が話を聞いたのは、藤原さんと猪木さんだけ」
プロレスラー鈴木みのるが“一人メシ”を語る「人生で一番うまかったメシはサラダかな」
「アントニオ猪木の後継者」を巡る因縁…当事者が対峙した1986年の凄惨マッチ
アントニオ猪木黒幕説も…「1999年の不穏マッチ」凶行を巡る“当事者の証言”
フワちゃんも参戦!“女子プロレス”をコロナ禍でも売上5倍にした経営の秘密
この記者は、他にもこんな記事を書いています




















