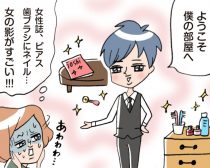“お笑い第7世代”は霜降り明星など。ところで第6世代、第5世代って誰?
“お笑い第七世代”という言葉を聞いたことがあるだろうか。最近、テレビやラジオなどさまざまなメディアで使われているワードで、霜降り明星、ハナコ、ミキ、四千頭身などの勢いのある若手芸人を指すらしい。でも、「そもそもなんで“7”なのか?」「第5世代、第6世代は誰のことを指しているのだろうか?」「お笑いの世代って?」など、わからないことも多い。
そこで長年にわたり独自でお笑い賞レースを研究してきた、お笑いルポライターtakahiro氏に、主な世代の代表芸人と、その世代ごとの特徴を尋ねた。
【過去記事】⇒霜降り明星が明かす「プロの芸人として本気になった瞬間」
「“お笑い第7世代”というのは、もともと霜降り明星のせいやがラジオで言い始めた言葉です。彼はのちに『20代の若手芸人のことを指していて、若手で集まって面白いことをしたいという意味合いで出した』と語っていますね。“7”という数字も明確に数えたわけではなく、何かしらのインパクトのある言葉でその世代をくくりたかったのでしょう」
そもそも、お笑いの世界で○○世代という言葉が使われ始めたのはいつ頃からなのか。
「“~~世代”という言葉が使われ始めたのは1980年代後半からですね。その頃はダウンタウン、ウッチャンナンチャン、とんねるずの3組が、ゴールデンに冠番組を持っていて同世代の中では抜きん出ていました。その3組と上の世代と区別する意味で、“第3世代”と言い始めたんです」
そのあと、1990年代に登場してきたナインティナインやロンドンハーツを“第4世代”と呼ぶように。ただそれ以降、ゴールデンに代表的な冠番組を持つ若手がそれほど出てこなかったと語る、takahiro氏。
「2000年初頭はネタ見せ番組が流行しました。『エンタの神様』や『爆笑オンエアバトル』などの看板番組があって、そこで多くの若手がしのぎを削っていた。たとえば、アンジャッシュ、バカリズム、陣内智則、フットボールアワーなどを“第5世代”と呼んでもいいでしょう」
2010年代に近くなると、ネタ見せ番組はやや減少傾向に。
「この時期に活躍した“第6世代”と呼べる芸人は、ネタだけでなく“トーク力”も試されていた世代と言えます。『アメトーク』などのバラエティ番組で、ひな壇でトークして光る芸人が求められている感はありましたね。ネタだけじゃなくて、フリートークができないと売れない。ジャルジャル、平成ノブシコブシ、三四郎、オードリー、NON STYLEなどが、この世代の代表です。
そこから2018年になり、M-1で霜降り明星が優勝するわけです。前年覇者のとろサーモンからは10歳以上若返っており、世代交代感は強まりました。そこから霜降り明星がブレイクし、若手がどんどん売れてきた。ゆりやんレトリィバァ、EXIT、宮下草薙など、いまテレビで活躍している20代の若手芸人を“第7世代”と定義できるでしょう」
第7世代は霜降り明星せいやがきっかけ
1
2
【関連キーワードから記事を探す】
『おもしろ荘』出演で仕事は10倍に。話題の“女性筋肉芸人”が語る過去「去年の4月までは、死んだような顔でバイトばかりしていました」
「もともとは俳優志望」のホンジャマカ石塚。お笑いに対して真剣に向き合う動機になった「マネージャーの一言」
相方の恵とは「年に1度も会っていない」 。それでもホンジャマカ石塚が「コントをやるなら恵」と断言する理由
“クズっぷり”が炎上「ガッポリ建設」小堀が明かす番組出演の裏側「ザ・ノンフィクションには感謝しています」
「エンタの神様」「あらびき団」で活躍した57歳芸人の今。月の収入は100万円から7万円に…
この記者は、他にもこんな記事を書いています