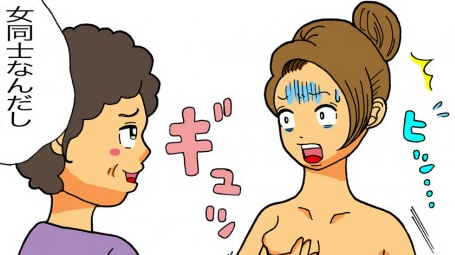“禁煙ファシズム”の危険性は?
“禁煙ファシズム”の危険性は?
「健康への悪影響から県民を守る」という美しい言葉を謳う一方、飲食店経営者に多大な負担を押し付け、業界の混乱を生み出している神奈川県条例。非喫煙者でありながら”禁煙ファシズム”を批判するジャーナリストの斎藤貴男氏は、その行きすぎた内容を”社会的な暴力”と指摘する。
「確かに、喫煙は疾病のリスクを伴うかもしれない。でも、それは、ほとんどの喫煙者が理解していること。そのうえで自ら進んで取り入れているんだから、それを他人が押し付けがましく騒ぎ立てる必要はないと私は思うんです」
それは、周りの人への”受動喫煙の影響”についても同じ。そもそも”副流煙”は、外気にさらされて希薄した煙。「店の中でわずかな時間を居合わせただけで肺がんになってしまう、という性格のものではない」と斎藤氏は説明する。
「タバコの煙が嫌だという人はいるでしょう。でも、とどのつまり感情の問題です。過敏になって『飲食店から喫煙者を閉め出せ』と言うのは異常。しかも、当事者同士で解決が試みられる前に、いきなりお上が現れるとは……。『存在自体が迷惑だ!』という小学生のイジメのような発想も、権力が人々の暮らしに安易に介入しようとする姿勢も、どうかしてます」
しかし、今回の条例で何よりも問題なのは、喫煙者は悪人というあらぬ思い込みを生み出し、さらにはその対象に向けて、県庁が自由に権力を行使できるようになったことだと斎藤氏は述べる。
「このような条例が横行すると、”タバコの喫煙環境の確認”という名目で頻繁に立ち入り検査が行われるようになる可能性があります。その対象が県庁にとって好ましくない店だった場合は、適当な罪名を店に擦り付け、営業できないようにつるし上げられることもありえる。さらに怖いのが権力を笠に着た一般人が出てくること。『あの店は条例違反だ!』などとブログやツイッターでの密告や嫌がらせがまかり通るようになるでしょう」
仮にこのような条例が全国へ広がれば、将来的には資金力の乏しい個人経営の店が街から姿を消すという事態にも。そのような社会をつくらないためにも、条例には冷静な目を向ける必要があるのだ。
【斎藤貴男氏】
’58年、東京都生まれ。
社会病理をテーマに活躍するジャーナリスト。
主な著作に『カルト資本主義』(文春文庫)、
『消費税のカラクリ』(講談社現代新書)など
取材・文/柴崎卓郎 藤村はるな 渡辺トモヒロ
イラスト/テラムラリョウ
撮影/山川修一(本誌)
データ出典:富士経済「外食産業マーケティング便覧2010(総括編)」
― 神奈川発[禁煙ファッショ]が飲食業界を滅ぼす!【8】 ―
この特集の前回記事
【関連キーワードから記事を探す】
愛煙家こそ“VAPE”を必携すべき理由。喫煙者100人調査でわかった
東京・大手町にある“愛煙家のオアシス”的カフェ。「豊かな時間へのこだわり」が随所にあった
新たばこデバイス「ウィズ2」×「大衆酒場 ネオトーキョー」が開催する期間限定イベント
愛煙家にとってのアミューズメント「たばこと塩の博物館」が面白い
東京に続いて大阪も“上乗せ”禁煙条例。喫煙所の整備を疎かにしてはならない
清野とおる×パリッコが語る、飲み歩いて気づいたこと「どこの街にも、キーマンはいる」
漫画家・清野とおる × 酒場ライター・パリッコ 書籍『赤羽以外の「色んな街」を歩いてみた』発売!
メダカすくいに救われた「水道橋」の夜/清野とおる×パリッコ
不動産屋はウソをつく。損しないために知っておきたい3つの“単語”
茨城県が魅力度ランキング最下位脱出!県民に直撃レポートしてみた