グーグルが「中国の検閲つき検索エンジン」開発を中止すると誰がトクするか?/ひろゆき
― ひろゆきのネット炎上観察記 ―
▼検閲つき検索エンジン開発。グーグル社員が反旗の狼煙
 「Don’t Be Evil(邪悪になるな)」。そんなモットーを創業時に掲げていたグーグルが揺らいでいる。中国政府のネット検閲に対応した検索エンジン「ドラゴンフライ」の開発に対し、同社従業員が「国家が国民を監視する検索エンジンの開発停止を求める」との声明を発表したからだ。ネット上では賛否両論、「社員がまともでよかった」「代わりにどこかがやるだろ」などの声が。
(追記:12月11日、米下院で開かれた公聴会で、「ドラゴンフライ」について質問されたグーグルのスンダー・ピチャイCEOは「社内で検討はしたが、中国で検索サービスを立ち上げる予定はない」と答えた。17日、「プロジェクトは実質的に終了」と報じた米メディアも)
上場企業の経営者は、利益を上げないと株主に排除されたりします。だもんで、中国という巨大市場(※1)を捨てるという選択ができないので、中国の決めたルールに従って中国でビジネスをしないといけないわけです。
そんなルールにグーグルの一部の社員が抗っているってのが、ネット上で話題になっていたりします。
中国政府は「金盾」(※2)で、国民に知られたくない情報を見せないようネット上の情報を検閲したり、接続できるサイトを制限しています。なんで、グーグルは中国向けに検閲つき検索エンジンをつくっているわけですけど、一部の従業員が「弱い立場にある者を強力に抑えつけるためのテクノロジーに反対している」ってな声明を出して、会社の決定に反対していたりするわけです。
グーグルが創業時に掲げていたモットーに「Don’t Be Evil」ってのがあるんですけど、何がEvilかってのは、定義の問題だったりするわけで、「検閲は悪いことではなくて必要なこと」って解釈もできちゃうんですよね。。。ちなみに、このモットーは’15年(※3)に「Do The Right Thing(正しいことをしよう)」に改変されていたりもするんですよね。
「Don’t Be Evil(邪悪になるな)」。そんなモットーを創業時に掲げていたグーグルが揺らいでいる。中国政府のネット検閲に対応した検索エンジン「ドラゴンフライ」の開発に対し、同社従業員が「国家が国民を監視する検索エンジンの開発停止を求める」との声明を発表したからだ。ネット上では賛否両論、「社員がまともでよかった」「代わりにどこかがやるだろ」などの声が。
(追記:12月11日、米下院で開かれた公聴会で、「ドラゴンフライ」について質問されたグーグルのスンダー・ピチャイCEOは「社内で検討はしたが、中国で検索サービスを立ち上げる予定はない」と答えた。17日、「プロジェクトは実質的に終了」と報じた米メディアも)
上場企業の経営者は、利益を上げないと株主に排除されたりします。だもんで、中国という巨大市場(※1)を捨てるという選択ができないので、中国の決めたルールに従って中国でビジネスをしないといけないわけです。
そんなルールにグーグルの一部の社員が抗っているってのが、ネット上で話題になっていたりします。
中国政府は「金盾」(※2)で、国民に知られたくない情報を見せないようネット上の情報を検閲したり、接続できるサイトを制限しています。なんで、グーグルは中国向けに検閲つき検索エンジンをつくっているわけですけど、一部の従業員が「弱い立場にある者を強力に抑えつけるためのテクノロジーに反対している」ってな声明を出して、会社の決定に反対していたりするわけです。
グーグルが創業時に掲げていたモットーに「Don’t Be Evil」ってのがあるんですけど、何がEvilかってのは、定義の問題だったりするわけで、「検閲は悪いことではなくて必要なこと」って解釈もできちゃうんですよね。。。ちなみに、このモットーは’15年(※3)に「Do The Right Thing(正しいことをしよう)」に改変されていたりもするんですよね。
 「Don’t Be Evil(邪悪になるな)」。そんなモットーを創業時に掲げていたグーグルが揺らいでいる。中国政府のネット検閲に対応した検索エンジン「ドラゴンフライ」の開発に対し、同社従業員が「国家が国民を監視する検索エンジンの開発停止を求める」との声明を発表したからだ。ネット上では賛否両論、「社員がまともでよかった」「代わりにどこかがやるだろ」などの声が。
(追記:12月11日、米下院で開かれた公聴会で、「ドラゴンフライ」について質問されたグーグルのスンダー・ピチャイCEOは「社内で検討はしたが、中国で検索サービスを立ち上げる予定はない」と答えた。17日、「プロジェクトは実質的に終了」と報じた米メディアも)
「Don’t Be Evil(邪悪になるな)」。そんなモットーを創業時に掲げていたグーグルが揺らいでいる。中国政府のネット検閲に対応した検索エンジン「ドラゴンフライ」の開発に対し、同社従業員が「国家が国民を監視する検索エンジンの開発停止を求める」との声明を発表したからだ。ネット上では賛否両論、「社員がまともでよかった」「代わりにどこかがやるだろ」などの声が。
(追記:12月11日、米下院で開かれた公聴会で、「ドラゴンフライ」について質問されたグーグルのスンダー・ピチャイCEOは「社内で検討はしたが、中国で検索サービスを立ち上げる予定はない」と答えた。17日、「プロジェクトは実質的に終了」と報じた米メディアも)
倫理観や正義感で手を縛ると、グーグルは中国企業に負ける
1
2
西村博之(にしむらひろゆき)1976年、神奈川県生まれ。東京都・赤羽に移り住み、中央大学に進学後、在学中に米国・アーカンソー州に留学。1999年に開設した「2ちゃんねる」、2005年に就任した「ニコニコ動画」の元管理人。現在は英語圏最大の掲示板サイト「4chan」の管理人を務め、フランスに在住。たまに日本にいる。週刊SPA!で10年以上連載を担当。新刊『賢い人が自然とやっている ズルい言いまわし』
記事一覧へ
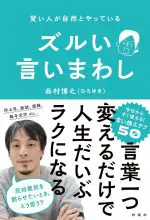 | 『賢い人が自然とやっている ズルい言いまわし』 仕事やプライベートで言葉に困ったとき…ひろゆきなら、こう言う! 50のシチュエーション別に超具体的な「言い換え術」を伝授。  |
 | 『ざんねんなインターネット』 日本のインターネット上で起こる様々な炎上事件や犯罪行為をどう見てきたのか? 満を持して出す、本気の「インターネット批評本」!  |
 | 『僕が親ならこう育てるね』 2ちゃんねる創設者・ひろゆき氏の新刊は“教育&子育て論” ※本の著者印税は、児童養護施設へのパソコン寄贈に充てられます。  |
記事一覧へ
【関連キーワードから記事を探す】
「Googleフォト」無制限アップロード中止。代わりの無料・無制限サービスはある?
Google全世界停止で露呈した「Google Home」の落とし穴。電気がつかない
異なる動画サービスをリモコンで管理!動画三昧にピッタリの新型「Chromecast」
詐欺アプリに引っかかった…『フォートナイト』泥仕合訴訟で思い出す苦い過去
「Googleマップ」でバスの位置情報がリアルタイム表示に!最新便利機能をまとめみた
ひろゆきが考える「“インターネットの嘘”を見抜ける人になる方法」
「インターネットが遅い…」3つの原因と解決法を家電販売員が解説
「公営団地」ネット回線ひけない問題、団地の自治会が障壁に
あれからどうしてる? 人気の「テキストサイト」たちの今
ネットで稼ぐのは悪だった…20年前から“文字だけサイト”を続けるカリスマたち
【ひろゆきの兵法 第3巻】自分を犠牲にしてまで「親の面倒」は見なくていい、と断言できるわけ
【ひろゆきの兵法 第2巻】結婚できない氷河期世代の男女に残された、最後の道とは?
新連載【ひろゆきの兵法 第1巻】国は僕らが困っても助けてくれない。就職氷河期世代はどう生き抜くべきか?
【ひろゆき構文・最終回】「失礼なことを言う人」がいるとき、相手に損をさせる言い方とは…
【ひろゆき構文】「大物と仕事した」アピールをされたとき、マウンティングをやめさせる言い方とは…
この記者は、他にもこんな記事を書いています




















