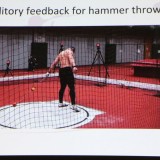室伏広治が考える「ウェアラブルとスポーツ」の未来
ウェアラブルの未来を考える「Wearable Tech Expo in Tokyo 2015(ウェアラブルテックエキスポ)」が7日、東京ビッグサイトTFTホールで開幕した。
昨今、スポーツの練習やコーチングツールとして「ウェアラブル・デバイス」活用の動きが加速している。最近では「FIVBワールドカップバレーボール2015」の中継で、選手の心拍数を可視化しリアルタイム放映したことが話題となった。
今回の「“連携”か“創造”か。スポーツ×テクノロジーが向かうべき未来」と題した講演には、オリンピアンでありながら、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の理事を務める室伏広治氏らが登壇した。
⇒【写真】はコチラ https://nikkan-spa.jp/?attachment_id=932124
――室伏さんはスポーツの研究者として、どのような活動を行ってきたのか。
室伏広治「アスリートとして競技に参加すると同時に、モーションセンサーの研究をしてきました。ハンマーが加速しているかどうかを音によってフィードバックし、自分の動作によるハンマーの加速を確認するものです。ハンマー投げは、野球のボールのように手元に投てき物がないので、その加速がわかりにくく、自分がものすごく回っていると思ってもハンマーは全然回っていないという現象があります。そこで、エネルギーがどれくらい伝わっているかを音に変換することを、ロンドン五輪の前に始めました」
――一流のアスリートでありながら、こうした研究を始めたきっかけは何だったのか。
「年齢を重ねると、むやみにカラダを動かしても怪我をしてしまいますから、自分の動きが直接ハンマーに伝わっているかを確認しながらやることが大事で、こうした研究がメダルに繋がったんじゃないかと思います。センサーは人工知能というか、第六感として考えていて、加速しているかどうかが音によってわかるということは、ある意味で第六感的な役割を果たして、それをフィードバックして運動するというパターンをつくることができるんです」
――スポーツにテクノロジーを導入することは大切なのか。
「やっぱりスポーツは、どうしても自分の感覚だけで一生懸命やっていると全然違う方向に行ってしまうことがあります。限られた時間とエネルギーでいかに成績を残すかを考えると、トップアスリートを育成する上では、スポーツ科学やエビデンスをベースにすることが必要だと考えています」
――こうした興味は選手として生まれたのか、研究者として生まれたのか。
「テクノロジーによって選手寿命を延ばしたり、カラダに負担のないやり方を考えたり、まだまだスポーツは可能性があります。スポーツ科学やテクノロジーが可能性を広げると思うと楽しみですね。実際にこういった研究が、ゴルフや野球などのスイングするスポーツで製品化されています。やはり『再現性』ということが大事で、一度だけトップになるのではなく再現して同じ成績を残そうと思うと、データを継続して見ていくことが大事になってくるんじゃないでしょうか」
――研究を踏まえ、今後どういったセンサーが開発されるといいだろうか。
「ただ飛距離を近づけようとすると選手によって隔たりが出ると思うんですけど、ある競技のトップ選手の音のデータがあれば、その音を聞いてその音に近づけようとか、加速するメカニズムを近づけようだとか、もうちょっと具体的な目標になってメダルに到達できる人も増えてくると考えています」
 ――フジテレビのバレーボール中継では、選手の心拍数が可視化され、緊張感やコンディションを分析している。選手の立場としてはどんな気持ちなのか。
「これは僕もわからないところがありまして、心拍が速いほうが疲れてパフォーマンスが落ちるのかというとまた別の話で、選手の中には抵抗のある人がいるかもしれません。心拍以外にもスポーツの要素で大事なものはありますし、競技やポジションによってずいぶん特徴が違うので、何が必要なデータなのかがまだわかっていない気がするんですよね。種目によっては心拍が大事だということと、個別性というのも考えなきゃいけないし、競技性も考えなきゃいけない。私なんかはスポーツ心臓で、心拍はものすごくゆっくりなんですよね」
――一方で、最初からウェアラブル・デバイスやARを使用することを前提とした新しいスポーツ「テクノスポーツ」を生み出す動きも登場している。
「スポーツっていうのは、我々が思っているよりも意外と範囲が広いものだと思うんですよね。これから新しいスポーツがどんどん出てくる可能性もありますし、既存のスポーツも古い歴史にこだわっているだけではなくて、競技者も観客も楽しめるという視点でリノベーション、イノベーションをどんどんしていかない限りは、スポーツの生き残りにも関わってくると思います」
――2016年にはスイスでサイバー義体オリンピック「Cybathlon(サイバスロン)」が開催され、超人スポーツ協会や世界ゆるスポーツ協会など、スポーツの定義そのものが拡大し、曖昧となってきている。
「ひとつ忘れちゃいけないのが、機械を開発するのか、人のカラダの機能を開発するのかということをどこかで考えなきゃいけなくて、普段の生活で自分のカラダの機能が改善したり助けたりするものなのか、助けてくれるけれども、いつの間にか自分の力が落ちちゃったということもあると思うんです。自分のカラダの能力を開発していくのがアスリートなので、その反面、新しいテクノロジーと一体になるとどんなすごいことができるのか楽しみですね」
――フジテレビのバレーボール中継では、選手の心拍数が可視化され、緊張感やコンディションを分析している。選手の立場としてはどんな気持ちなのか。
「これは僕もわからないところがありまして、心拍が速いほうが疲れてパフォーマンスが落ちるのかというとまた別の話で、選手の中には抵抗のある人がいるかもしれません。心拍以外にもスポーツの要素で大事なものはありますし、競技やポジションによってずいぶん特徴が違うので、何が必要なデータなのかがまだわかっていない気がするんですよね。種目によっては心拍が大事だということと、個別性というのも考えなきゃいけないし、競技性も考えなきゃいけない。私なんかはスポーツ心臓で、心拍はものすごくゆっくりなんですよね」
――一方で、最初からウェアラブル・デバイスやARを使用することを前提とした新しいスポーツ「テクノスポーツ」を生み出す動きも登場している。
「スポーツっていうのは、我々が思っているよりも意外と範囲が広いものだと思うんですよね。これから新しいスポーツがどんどん出てくる可能性もありますし、既存のスポーツも古い歴史にこだわっているだけではなくて、競技者も観客も楽しめるという視点でリノベーション、イノベーションをどんどんしていかない限りは、スポーツの生き残りにも関わってくると思います」
――2016年にはスイスでサイバー義体オリンピック「Cybathlon(サイバスロン)」が開催され、超人スポーツ協会や世界ゆるスポーツ協会など、スポーツの定義そのものが拡大し、曖昧となってきている。
「ひとつ忘れちゃいけないのが、機械を開発するのか、人のカラダの機能を開発するのかということをどこかで考えなきゃいけなくて、普段の生活で自分のカラダの機能が改善したり助けたりするものなのか、助けてくれるけれども、いつの間にか自分の力が落ちちゃったということもあると思うんです。自分のカラダの能力を開発していくのがアスリートなので、その反面、新しいテクノロジーと一体になるとどんなすごいことができるのか楽しみですね」
 <取材・文・撮影/北村篤裕>
<取材・文・撮影/北村篤裕>
 ――フジテレビのバレーボール中継では、選手の心拍数が可視化され、緊張感やコンディションを分析している。選手の立場としてはどんな気持ちなのか。
「これは僕もわからないところがありまして、心拍が速いほうが疲れてパフォーマンスが落ちるのかというとまた別の話で、選手の中には抵抗のある人がいるかもしれません。心拍以外にもスポーツの要素で大事なものはありますし、競技やポジションによってずいぶん特徴が違うので、何が必要なデータなのかがまだわかっていない気がするんですよね。種目によっては心拍が大事だということと、個別性というのも考えなきゃいけないし、競技性も考えなきゃいけない。私なんかはスポーツ心臓で、心拍はものすごくゆっくりなんですよね」
――一方で、最初からウェアラブル・デバイスやARを使用することを前提とした新しいスポーツ「テクノスポーツ」を生み出す動きも登場している。
「スポーツっていうのは、我々が思っているよりも意外と範囲が広いものだと思うんですよね。これから新しいスポーツがどんどん出てくる可能性もありますし、既存のスポーツも古い歴史にこだわっているだけではなくて、競技者も観客も楽しめるという視点でリノベーション、イノベーションをどんどんしていかない限りは、スポーツの生き残りにも関わってくると思います」
――2016年にはスイスでサイバー義体オリンピック「Cybathlon(サイバスロン)」が開催され、超人スポーツ協会や世界ゆるスポーツ協会など、スポーツの定義そのものが拡大し、曖昧となってきている。
「ひとつ忘れちゃいけないのが、機械を開発するのか、人のカラダの機能を開発するのかということをどこかで考えなきゃいけなくて、普段の生活で自分のカラダの機能が改善したり助けたりするものなのか、助けてくれるけれども、いつの間にか自分の力が落ちちゃったということもあると思うんです。自分のカラダの能力を開発していくのがアスリートなので、その反面、新しいテクノロジーと一体になるとどんなすごいことができるのか楽しみですね」
――フジテレビのバレーボール中継では、選手の心拍数が可視化され、緊張感やコンディションを分析している。選手の立場としてはどんな気持ちなのか。
「これは僕もわからないところがありまして、心拍が速いほうが疲れてパフォーマンスが落ちるのかというとまた別の話で、選手の中には抵抗のある人がいるかもしれません。心拍以外にもスポーツの要素で大事なものはありますし、競技やポジションによってずいぶん特徴が違うので、何が必要なデータなのかがまだわかっていない気がするんですよね。種目によっては心拍が大事だということと、個別性というのも考えなきゃいけないし、競技性も考えなきゃいけない。私なんかはスポーツ心臓で、心拍はものすごくゆっくりなんですよね」
――一方で、最初からウェアラブル・デバイスやARを使用することを前提とした新しいスポーツ「テクノスポーツ」を生み出す動きも登場している。
「スポーツっていうのは、我々が思っているよりも意外と範囲が広いものだと思うんですよね。これから新しいスポーツがどんどん出てくる可能性もありますし、既存のスポーツも古い歴史にこだわっているだけではなくて、競技者も観客も楽しめるという視点でリノベーション、イノベーションをどんどんしていかない限りは、スポーツの生き残りにも関わってくると思います」
――2016年にはスイスでサイバー義体オリンピック「Cybathlon(サイバスロン)」が開催され、超人スポーツ協会や世界ゆるスポーツ協会など、スポーツの定義そのものが拡大し、曖昧となってきている。
「ひとつ忘れちゃいけないのが、機械を開発するのか、人のカラダの機能を開発するのかということをどこかで考えなきゃいけなくて、普段の生活で自分のカラダの機能が改善したり助けたりするものなのか、助けてくれるけれども、いつの間にか自分の力が落ちちゃったということもあると思うんです。自分のカラダの能力を開発していくのがアスリートなので、その反面、新しいテクノロジーと一体になるとどんなすごいことができるのか楽しみですね」
 <取材・文・撮影/北村篤裕>
<取材・文・撮影/北村篤裕>
【関連キーワードから記事を探す】
ヨガ、海外ドラマ、料理… スマートグラスを1日のあらゆる場面で使えるか実験!
AV観賞しながら、彼女の愚痴を聞いてみた
通勤電車内や仕事中にAV鑑賞したらどうなるか?
“ながら”OKの最新ARガジェットで仕事の効率化を図る方法
使いこなせば超便利! 今すぐ買えるオススメ[ウェアラブル端末]3選
トラッキングデータで“魔球”好きの野球ファンも見方が変わる!?
Jリーグを「トラッキングデータ」で楽しむ! 生配信でデータ化する最新技術の裏側
眠気のレベルを教えてくれる…etc. メガネ型ウェアラブル「JINS MEME」の特徴
JINSが開発したメガネ型ウェアラブル「JINS MEME」のメリット&デメリット
室伏広治が考える「ウェアラブルとスポーツ」の未来
ユニクロのセルフレジって何がどうなってるの…「ギズモード・ジャパン」が身近なテクノロジーの疑問に明朗回答
「ノイキャン」はなぜ周囲の音が消えるの?テクノロジー情報サイト「ギズモード・ジャパン」が日常の中のテクノロジーを解説
『レジリエンスの時代 再野生化する地球で、人類が生き抜くための大転換』 著者のジェレミー・リフキンさんに聞く
AIが「人類を削除したほうが合理的」と判断する日はくるのか?
AIに監視される時代がすぐそこに…AI防犯システムの問題点と可能性